大東亜戦争敗戦時アジア諸国の首脳発言
太平洋戦争におけるわが国の戦争被害
「世界から恐れられた7人の日本人」
「大東亜戦争の英雄の日本人1」
「大東亜戦争の英雄の日本人2」
「大東亜戦争の英雄の日本人3」空の要塞B29撃破とB29撃墜王
「大東亜戦争の英雄の日本人4」陸軍エースパイロット撃墜数
「大東亜戦争の英雄の日本人5」海軍エースパイロット撃墜数
「大東亜戦争技術者」
「大東亜戦争技術者2」
「大東亜戦争石油」
日米開戦前日米交渉(アメリカが日本に実質的最後通牒(日本の南部仏印撤退などの譲歩案に))
第2節 国際石油会社の誕生と発展
このページを印刷する場合はこのリンクをクリックしてください。
このページは、目次の中の資料編の中の石油産業の歴史:第1章 国際石油産業の中の第2節 国際石油会社の誕生と発展のページです。
世界市場におけるロシアの台頭
スタンダードとシェルの競争
ロイヤル・ダッチ/シェルグループの成立
7大メジャーズの出現
第一次世界大戦後の列強による資源獲得競争
国際石油カルテルの成立
1. 世界市場におけるロシアの台頭
ロシアの石油産業は1870年代中ごろから急速に発展し、原油生産量は1870年のわずか20万バレルから、1890年には2,900万バレルに増大した(表 1-2-1)。
ロシア灯油がオーストリア、ハンガリー、英国に初めて姿を現したのは1883年であったが、2年後には9ヵ国で、さらにその2年後には17ヵ国で米国灯油と競争するほどになった。発展の原動力となったのは、後年、ノーベル賞で名前を馳せる、スウェーデンのノーベル兄弟(Robert Nobel、Ludwig Nobel)とフランスのロスチャイルド家(Rothschilds)であった。
ノーベル兄弟は1875年、ロシアの石油地帯であるバクーに進出して製油所を建設し、続いて産油部門にも参入、ほどなく諸外国に販売設備をもつまでに成長した。この過程で、米国から削井機を導入、原油パイプラインや鉄道タンク車など輸送手段を整備、ロシア国内で重油市場を開拓、内航船ではあったが世界で最も早く鋼鉄船により中味輸送を実施(世界最初のタンカー)、同じく世界最初の連続蒸留法を企業化するなど、様々な革新を進めていった。
なお、1879年にはノーベル兄弟産油会社(The Nobel Brothers Petroleum Production Co.)が設立された。こうしてノーベル兄弟は、1888年にはロシア灯油の3分の1を生産するまでに成長していた。
表 1-2-1 主要国の原油生産量の推移(1930年以前) [PDF 51KB]
一方、ロスチャイルドは、バツーム鉄道に対する融資と交換に、バクーの石油権益を獲得し、1883年にカスピアン・アンド・ブラックシー・ペトロリアム(一般にロシア語の頭文字をとってBnito:ブニトと呼ばれた)を設立した。ブニトは、多数の小規模製油業者と契約してロシア灯油の最大輸出業者となり、ヨーロッパでの販売網の整備を進めるとともに、1880年代後半には東洋市場へも進出した。
このようなロシア石油産業の著しい発展によって、ロシア灯油の世界市場シェアは、1884年の3%から1889年には22%にまで上昇した。
これに対して、米国灯油のシェアは97%から78%へと低下し、ロシア灯油は、米国灯油にとって強力なライバルとして、無視できない存在となった。
ページの先頭へ移動します。
2. スタンダードとシェルの競争
英国の貿易商マーカス・サミュエル(Marcus Samuel)は、1891年にブニトを支配するロスチャイルドとの間で、1900年を期限とするロシア灯油の独占販売契約を締結した。これは、ロシア灯油の東洋市場向け大量輸出の道をひらく画期的な出来事であった。
マーカス・サミュエルは、1897年にシェル運輸貿易会社(Shell Transport and Trading Company:以下シェルと略す)を設立して、彼の石油事業を継承させた。
こうして、1890年代には米国灯油とロシア灯油、つまりスタンダードとシェルの衝突は不可避となった。
この間、スタンダードは1880年代末ごろから、ヨーロッパ主要市場で4分の3の販売シェアを頑強に維持する代わりに、重要性を増しつつある東洋市場へのロシア灯油の進出を妨害しない、という作戦をとったといわれる。実際にも、ロシア灯油の進出は特に東洋市場でめざましかった。
ページの先頭へ移動します。
3. ロイヤル・ダッチ/シェルグループの成立
スタンダードとシェルに支配されるようになった東洋市場に、1890年代後半には強力な新勢力としてロイヤル・ダッチ(Royal Dutch、正式名は Royal Dutch Petroleum)が登場した。
1890年に設立されたオランダの石油会社ロイヤル・ダッチは、蘭印(オランダ領東インド:現インドネシア)に属するスマトラ東海岸で生産される原油を精製するため、パンカラン・ブランダンに製油所を完成させ、1892年にシンガポールやマレー半島向けの灯油の輸出を開始した。その4年後には、蘭印からアジア・大洋州(日本、中国、東インド、オーストラリア)向けの輸出量は300万バレル以上に達し、米国からの同地域向け輸出量にほぼ匹敵するに至った。
この三者は激しい販売競争を行うと同時に、提携相手の模索にも力を入れた。1901年、シェルはスタンダードとロイヤル・ダッチの双方と並行的に提携交渉を進めていたが、同年12月、スタンダードとの交渉を打ち切って、ロイヤル・ダッチとの提携について原則的に合意し、いわゆる「英蘭協定」(British-Dutch Agreement)を締結した。
この協定だけでは、シェルとロイヤル・ダッチの販売競争は収まらなかったが、1903年6月、両者にロスチャイルドが加わって、「東方でのお互いの競争をやめるために」三者合弁(出資比率は対等)のアジアチック・ペトロリアム(Asiatic Petroleum Co.)が設立された。ロスチャイルドは、ブニトによって東洋市場向けロシア灯油をシェルに供給していただけでなく、ロイヤル・ダッチにもロシア灯油を供給していた。
また、1907年にはロイヤル・ダッチとシェルの一本化が成立し、前者60%、後者40%の持ち分によって、両者の事業を共同化することになった。これにより、ロイヤル・ダッチ/シェルグループ(以下シェルと略す)が形成され、アジアチックもこの新組織に組み込まれた。
ページの先頭へ移動します。
4. 7大メジャーズの出現
このようにして、米国の石油資源に基盤をおくロックフェラーのスタンダードグループと、東南アジアの石油資源に基盤をおくシェルグループが二大勢力となったのである。
1908年、英国人ウィリアム・ノックス・ダーシー(William Knox D'Arcy)がペルシャ(現イラン)で最初の油田を発見したが、1909年には、これを母体として、後のブリティッシュ・ペトロリアム(現在のBP)の原形であるアングロ・ペルシャン石油会社(Anglo-Persian Oil Company)という、もう一つの国際石油企業が設立された。
一方、米国ではテキサス、カリフォルニアの各州で新しい油田の発見が相次ぎ、スタンダードグループ以外にも大きな石油会社が出現してきた。1901年にテキサス燃料会社(Texas Fuel Company:1903年にTexas Oil Companyに社名変更、後のテキサコ)、1907年にはガルフ石油会社(Gulf Oil Corporation)が設立された。
そして、1911年に米国のシャーマン反トラスト法(Sherman Antitrust Act of 1890)の適用により、持株会社としてスタンダード石油グループを統轄していたニュージャージー・スタンダード石油会社(Standard Oil Company of New Jersey:後のエクソン、現在のエクソンモービル)は持株会社の地位を失い、スタンダードグループを構成していた30を超える石油会社は、独立した石油会社として、互いに競争することとなった。この中から、カリフォルニア・スタンダード石油会社(Standard Oil Company of California:後のシェブロン)やニューヨーク・スタンダード石油会社(Standard Oil Company of New York:後のモービル、現在のエクソンモービル)が発展していった。
スタンダード石油3社(ニュージャージー/カリフォルニア/ニューヨーク)に、シェル、アングロ・ペルシャン、テキサス、ガルフを加えた国際石油企業は一般に7大メジャーズ(Majors)と呼ばれた。20世紀初頭に7大メジャーズを中心とする国際石油産業の体制はほぼ整ったのである。
ページの先頭へ移動します。
5. 第一次世界大戦後の列強による資源獲得競争
1914年に始まり、1918年に終わった第一次世界大戦では、飛行機、戦車、重油専焼艦艇などが活躍し、石油が戦略的にきわめて重要な物資であることを世界的に認識させた。こうして、動力エネルギー源としての石油の価値が高まっていき、「灯油の時代」から「動力あるいはエネルギーの時代」へと移っていった。
米国の原油生産量は、1910年には2億バレルを越え、世界の60%以上を生産しており(表 1-2-1)、1921年には世界の石油貿易量の50%以上を輸出していた。しかも、その輸出量の87%は原油ではなく、石油製品であった。1920年代に入ると、米国にも石油資源の枯渇を懸念する声が高くなり、はじめて米国の大手石油会社が、製品市場だけでなく、石油資源を求めて国際的に動き出すようになった。
しかし米国の石油会社は、東半球の重要石油資源からは、ほぼ完全に締め出されていた。当時の中東の唯一の産油国ペルシャの石油利権は、英国のアングロ・ペルシャンに独占され、英国政府は第一次大戦勃発直前の1914年5月に、同社株式の過半数を獲得して立場を強化していた。
また、有望視されていたメソポタミア(現イラク)を含む、広大なオスマン・トルコ帝国の石油資源を対象として設立されたトルコ石油(Turkish Petroleum Co.)の持株比率は、1914年3月、英国、ドイツ両政府を含む関係者間協定によって、アングロ・ペルシャンが50%、シェルとドイツ国立銀行がそれぞれ25%と決まった。
その後、第一次世界大戦開戦後の1915年に英国、フランス両政府は秘密交渉を開始し、戦後の1920年4月のサンレモ協定によって、ドイツ国立銀行の持ち分25%をそのままフランス政府に与えることが決められた。これによってフランスは、大戦の戦訓に基づき石油供給源へ直接参入を果たした。サンレモ協定は、英仏石油連合の形成として世界的な反響を呼び、米国では石油業界、政界、報道機関に大きな衝撃を与えた。メソポタミアへの参入をねらう米国の石油会社と政府は、英国に対して「門戸開放」を求めて繰り返し抗議し、外交的緊張が高まった。
1922年6月、アングロ・ペルシャンがニュージャージー・スタンダード石油会社に対し、トルコ石油問題に関する代表団派遣を求めたのをきっかけに、問題は解決に向かったが、最終解決には1928年まで6年間を費やした。
ページの先頭へ移動します。
6. 国際石油カルテルの成立
アクナカリー協定の締結
第一次大戦直後にあった、ロシア革命による原油生産の混乱などを理由とする石油供給不安はごく短期間で解消し、3~4年後には、逆に供給過剰を露呈した。しかも1920年代後半、米国でオクラホマ州のセミノール、カリフォルニア州のケルトマンヒルズなど大油田の発見が相次ぎ、原油供給力は一層増大した。これに加えて米国外でも、ベネズエラ、ソ連、ペルシャなどで生産が増強された(表 1-2-1)。
石油供給過剰を背景として、ソ連石油への対応をめぐって対立していたシェルとニューヨーク・スタンダード石油会社は、1927年秋からインド、次いで英国、米国本土で激しい値引き競争を展開、その余波は我が国を含む世界主要地域に広がり、石油企業に壊滅的な打撃を与えた。
これを契機として、1928年9月、国際石油市場のビッグスリーであるニュージャージー・スタンダード石油会社、シェル、アングロ・ペルシャンは「アクナカリー協定」または「現状維持協定」と呼ばれる包括的なカルテル協定を締結した。
同協定は、全世界で生産を中止している油井の生産能力(Shut-in Production)が実際に消費される原油生産の60%に達し、過当競争が膨大な供給過剰をもたらしているとの前提に立って、米国外における各社の市場シェアを、将来とも原則として1928年当時のものに固定することを骨子としていた。これがつまり「現状維持」の原則である。
赤線協定の成立
同じころ、中東の石油資源支配の歴史が大きく進展した。すなわち、1928年7月、前述のように長期間の交渉が続いていたトルコ石油(1929年に社名をイラク石油に変更)の持株比率が決定し、米国石油会社としてニュージャージー・スタンダード石油会社とソコニー・バキューム石油会社(Socony-Vacuum Oil Company:ニューヨーク・スタンダード石油会社と潤滑油専業会社バキューム石油会社が1931年に合併して誕生)の参入が実現した。
これと同時に、主としてフランス側からの提案に基づいて、トルコ石油参加各社は、旧オスマン・トルコ帝国領土内で、実質的に石油利権の共同所有と共同操業を義務付けられた。その範囲は地図に赤線で示され、ペルシャとクウェートを除く中東の重要地帯のすべてを包含していた。このため、このときの協定は「赤線協定」と呼ばれるようになった。赤線協定は、英国、米国、フランス各国政府の承認のもとに締結され、単に国際石油会社間の協定にとどまらず、政府間協定の性格をも兼ね備えており、中東石油資源の支配構造に大きな影響を及ぼした。
石油が発見される以前のサウジアラビアも赤線協定の対象地域に含まれていたため、米国石油会社ながら同協定に参加していなかったカリフォルニア・スタンダードがここに注目し、交渉の末1933年に単独で石油利権の取得に成功した。この石油利権は、1936年にテキサス会社との共同所有になった。
このようにして、国際石油企業が相互に提携しあって、米国内を除く自由世界の主要石油資源を独占する体制が形成された。
さらに、1930年代に入ると、石油需要の拡大とその市場の国際的な発展のために、国際石油会社の再編成が実施された。すなわち、ニュージャージー・スタンダード石油会社とソコニー・バキューム石油会社が、スエズ運河から東の諸地域で共同して事業を行うため、1933年にスタンダード・バキューム石油会社(Standard-Vacuum Oil Co.:略称Stanvac)を折半出資で設立したほか、カリフォルニア・スタンダード石油会社とテキサス会社は、東半球全域で共同事業を営むために、1936年にカルテックス(Caltex、正式名はCalifornia Texas Oil Company)を設立した。
かかる状況下で、第二次世界大戦が始まったのである。この大戦は、軍需物資としての石油の重要性をさらに高める結果となり、国際経済上および国防上の観点から石油問題を単に大企業であるメジャーズのみの問題とせず、政府の外交・経済・国防政策上の問題とするに至ったのである。
北樺太石油
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%A8%BA%E5%A4%AA%E7%9F%B3%E6%B2%B9
この記事は良質な記事に選ばれています
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
北樺太石油株式会社
種類 株式会社
本社所在地 大日本帝国の旗 東京府東京市
設立 1926年(大正15年)6月7日
解散 1944年(昭和19年)7月1日
(帝国石油に吸収合併)
業種 鉱業
事業内容 北樺太における石油開発
歴代社長 中里重次
左近司政三
荒城二郎
公称資本金 1000万円
→1931年、2000万円に増資
主要株主 日本石油、日本鉱業、富国徴兵保険、三菱鉱業、三井鉱山(1940年5月31日時点)[1]
テンプレートを表示
北樺太石油の位置(サハリン州内)オハ(奥端)オハ(奥端)カタングリ(潟畔)カタングリ(潟畔)
北樺太油田の位置。その他東岸に試掘地が点在した。
北樺太石油株式会社(きたからふとせきゆかぶしきかいしゃ)は、かつて存在した日本の国策会社であり、昭和初期にソビエト連邦領の北樺太(北サハリン)で油田開発を行っていた。日ソ基本条約に基き日本が北樺太の石油利権を獲得した後の1926年(大正15年)に設立され、北樺太東海岸のオハのオハ油田、カタングリのカタングリ油田を中心に採掘を行った。艦船燃料として石油資源の確保を望む大日本帝国海軍の影響下で誕生した会社であり、海軍出身者が歴代社長に就任し、石油は基本的に海軍に納入された。1943年(昭和18年)まで採掘を行ったが、資金不足から試掘が進まず採油能力が低下したことに加えて、外交関係悪化に伴うソ連の事業妨害などから1930年代後半には業績は下り坂となった。1944年(昭和19年)にソ連の中立を維持するための外交材料として北樺太石油利権がソ連へ返還された後、帝国石油に吸収合併され消滅。なお本記事では、樺太での石油発見から日本の北樺太利権獲得までの経過についても触れる。
前史
樺太における石油発見
画像外部リンク
現在のゾートフ1号井の写真 - 記念井として保存されている[2]。
樺太における石油開発の歴史は、1880年にロシア帝国ニコラエフスクの毛皮商人イワノフがオハ川上流で石油の大露頭を発見したことに始まる[3]。イワノフは沿海州軍務知事に鉱区を求める請願を出したが、翌1881年に病没。1883年、イワノフの相続人に鉱区が認められたが、賃貸料の負担が重く事業を断念した。その後、1886年にアレクサンドロフスクの管区長リンデンバウムが樺太の探査を行い鉱区の請願を行った。これを知ったイワノフの娘婿のグリゴリー・ゾートフが鉱区獲得に乗り出し、1889年にオハの鉱業権を獲得して「サハリン石油工業ゾートフ組合」を設立した。ゾートフは地質調査を行ったものの資金不足となり1893年に組合は破綻する。1906年に改めて組合を設立し再起を図ったが、ゾートフは間もなく死去。事業を引き継いだ「サハリン石油鉱業ゾートフ相続人組合」が1909年にオハで初めて湧出に成功した(ゾートフ1号井)。しかし資金不足で1914年に鉱区を没収された[4]。
また、1892年にロイヤル・ダッチがドイツ人技師のフォードル・クレイを樺太に派遣。ロシアでは外国人の掘削が認められなかったため、クレイはロシアに帰化してヌトウォほかの試掘権を得た。ロイヤル・ダッチは採掘困難と判断して撤退したが、クレイは事業を継続。1902年にロンドンで「サハリン・アムール鉱山工業シンジケート」、1908年に天津で「支那石油会社」を設立したが資金不足となり、1912年にクレイが死んだ後、事業を継いだ彼の息子も1914年に税金滞納で鉱区を没収された[5]。
そのほか、ロシアで「サハリン探鉱会社」と「ペトログラード商会」が設立された。前者は法規違反で利権を失い解散したが、後者は「ロシア極東工業会社」と改称。さらにイギリス資本の「ファースト・サガレン・シンジケート」と合同して1910年に設立された「セカンド・サガレン・シンジケート」が、ロシア極東工業の利権の半分を譲り受け、2社により開発が進められた[6]。両社は鉱業権が1917年から18年に失効するため、有望鉱区の永久開発権をロシア政府へ請願したが、外国石油会社の反対に合い認められなかった[7]。
日本の北樺太利権獲得交渉
北辰会の設立に至るまで
艦船の燃料に石炭を使用していた日本海軍は、20世紀に入ると重油への移行を進めた。日露戦争末期の1905年(明治38年)に樺太を占領した際には、海軍は西海岸の石炭を調査したものの石油については積極的に調査を行わなかった。しかしその後、1908年(明治41年)に石炭・重油混焼の巡洋戦艦「生駒」を建造し、八八艦隊計画では重油を主燃料、石炭を従とするなど、石油資源への関心を高めていった[8]。
1912年(明治45年)、クレイの支那石油会社から日本での販売権を打診されていた松昌洋行の山本唯三郎が、インターナショナル石油顧問の石川貞治に依頼し、海軍の便宜を受けて現地調査を実施した[9][10]。北樺太油田は新潟や北海道の油田より優れているとの報告書を作成するが、日本企業は関心を示さなかった。石川は、1916年(大正5年)に桜井彦一郎、大隈信常、押川方義らを通じて大隈重信に働きかけ、海軍に1万円の助成金を要望したが断られる[11]。同年、桜井はロシアに行き北樺太油田の日露共同開発の内諾を得て、久原鉱業の久原房之助の後援を得ることになったが、1917年(大正6年)のロシア革命勃発により中断を余儀なくされた[12]。
その後も桜井は活動を続け、1917年10月にウラジオストクへ行き、北樺太西岸で炭鉱経営を行っていたイワン・スタヘーエフ商会を紹介される。同社は、セカンド・サガレン・シンジケートとロシア極東工業の利権が1918年までに消滅することに着目して支配人バトゥーインを日本へ派遣し、大隈重信に日露合弁の石油会社設立を打診した。大隈は久原房之助を紹介し、1918年5月に久原鉱業とスタヘーエフ商会の間で合弁契約が締結された[13]。同年、久原鉱業は北樺太に調査隊を送り、北樺太油田が有望であるとの結果を得た[14]が、オムスクの臨時全ロシア政府はなかなか許可しなかった[15]。なお海軍も1918年9月に宮本雄助機関中佐を北樺太に派遣。宮本は日本人として初めてオハ油田の調査を行い、有望との報告を行った[16]。この間、日本のほか英米資本も極東ロシアでの利権獲得に向けて行動していたことから、日本政府は1919年(大正8年)4月1日に北樺太の油田・炭田開発について、日露合弁で進め他国を排除し、国内企業の協同を図ることと政府援助の検討を閣議決定した。そして、従前から広く民間企業を集め事業を進める方針を打ち出していた海軍の働きかけにより、5月1日、久原鉱業、三菱商事、大倉商事、日本石油、宝田石油の5社が石油開発シンジケート「北辰会」を設立し、久原とスタヘーエフ商会の契約を引き継いだ[17][18]。
北辰会はスタヘーエフ商会による鉱区出願が未許可であったものの、ロシア官憲の了解を得て試掘作業に着手した。しかし、1920年(大正9年)にニコラエフスクで赤軍パルチザンに日本人が虐殺される尼港事件が発生し、北辰会の作業地バターシン(ボアタシン、ロシア語: Боатасин)にもパルチザンが襲来するおそれが生ずると、北辰会は作業を中止し徒歩で1ヶ月かけて南樺太の散江へ撤退した[19][20]。同年8月、日本軍は同事件の賠償を将来正当な政府が行うまでの「保障」として北樺太を軍事占領し、油田へ守備隊を派遣した[21][17]。北樺太に軍政を敷いた日本政府は、9月28日に北樺太の油田・炭田開発方針を閣議決定し[22]、海軍の指導監督下で北辰会は作業を再開した[23]。
1922年(大正11年)には北辰会に三井鉱山と鈴木商店が加わり、「株式会社北辰会」へ改組し、日本石油の橋本圭三郎が会長に就任した[24]。北辰会は各地で地質調査と試掘を行い、1923年(大正12年)にオハで採油に成功。翌年には海軍が初めて日本へ原油5,440トンを搬入した[25]。
シンクレア石油の利権獲得運動
ハリー・フォード・シンクレア
誕生したばかりのソ連は第一次世界大戦とロシア内戦により荒廃した国家を復興するため、1920年11月に「コンセッションの一般的な経済的・法的条件」を布告。外国資本への利権供与(コンセッション方式)により、天然資源開発などを進める方針を打ち出していた[26]。
こうした中、アメリカ合衆国の新興企業であるシンクレア石油会社(英語版)は、樺太・シベリア・中国での油田開発を目的に合弁企業の設立を日本に持ちかけた。この提案に対し鈴木商店が関心を示したが、海外資本の参入を避けたい日本政府は消極的な態度をとった[27]。このためシンクレア石油は極東共和国に接近し、1922年1月に北樺太油田の調査権・採掘権・販売権について仮契約を締結[28]。極東共和国がソ連に併合された後、シンクレア石油は1923年11月にソ連と利権の仮協定を締結し樺太へ油田調査隊を派遣しようとした。しかし、日本政府は同年4月24日の閣議で、シンクレア石油とソ連の契約を認めず、かつシンクレア石油の北樺太調査を拒否すると決定しており、調査を妨害した[29]。ハリー・フォード・シンクレア(英語版)社長はアメリカ政府の支援を得ようと国務省に働きかけたが、スタンダード・オイル寄りで対ソ交渉ではコーカサスの石油利権獲得に重点を置いていたチャールズ・エヴァンズ・ヒューズ国務長官は協力せず、さらにシンクレア社長が贈賄疑惑(ティーポット・ドーム事件)の発覚により信用を失ったため、日本との利権獲得競争に敗北。最終的に1925年2月、ソ連最高国民経済会議でシンクレア石油の利権契約の解消が承認された[30][31]。
北樺太油田利権の獲得
「日ソ基本条約」も参照
1921年以来、日ソ両国[注 1]は、日本軍の北樺太からの撤退とソ連政府の承認、尼港事件の解決に関して交渉を重ねたが、北樺太の資源利権も論点となっていた[32][33]。
1922年9月に極東共和国との間で開催された長春会議が決裂した後、日露協会会頭を務め日ソ国交樹立を目指していた後藤新平東京市長は、加藤友三郎総理大臣の了解を得て、1923年2月にソ連駐華全権代表アドリフ・ヨッフェを病気療養の名目で日本へ招いた。そして、後藤とヨッフェが私的会談を行った後、6月末から7月にかけヨッフェと帰国中の駐ポーランド公使川上俊彦の間で非公式予備協議が行われた。本協議では北樺太全域の日本への売却も議論された[注 2]が、売却価格を日本は1億5千万円、ソ連は15億ルーブル(当時の15億円)とそれぞれ主張し折り合わなかった[注 3]。しかし北樺太利権の供与はほぼ合意に至った[35][36]。
続いて1924年5月から駐華公使芳澤謙吉とソ連代表レフ・カラハンとの間で北京会議が行われた。日本に認める油田権益比率について、日本が60パーセント、ソ連が40パーセントを主張し対立。日本海軍は同時に交渉していた北樺太西海岸の炭田権益を放棄しても油田権益60パーセントの確保を主張したが、50パーセントとする外務省案で妥協。ソ連はなおも45パーセントを主張したが、レーニン没後1周年(1925年1月25日)までに条約締結を目指す意向から日本案の50パーセントで妥結した[37]。
ウィキソースに日ソ基本条約の原文があります。
1925年(大正14年)1月20日、日ソ基本条約を北京で締結。同条約第6条にソ連が日本に対し天然資源の開発に関する利権を供与する意向があることが明記され、条約の付属議定書(乙)で北樺太の油田利権内容を定めた[注 4]。その概要は以下の通り[39]。
日本軍の北樺太撤退[注 5]後、5か月以内に利権契約を締結する(本文)。
北樺太油田の5割を開発する利権を日本政府が推薦する事業者(コンセッション会社)へ与える(第1項)。
利権契約締結後1年内に定める1,000平方ヴェルスタの地域において試掘期間は5-10年(第2項)、油田開発利権の期間は40-50年とする(第4項)。
中里重次
同年6月、加藤高明総理大臣が国内の実業家100名を官邸に招き、北樺太油田利権のための会社設立に関する懇談会を開催。元海軍省軍需局長で燃料問題に係った経験を持つ[41]中里重次海軍中将を利権交渉代表および新会社の社長に決定した[24]。そして、利権交渉団は川上俊彦が顧問となり同年7月にモスクワへ向かった。正式会談24回、技術会議約20回、小委員会十数回を行い、途中交渉が難航し何度か決裂の危機があったものの、同年12月14日に日ソ基本条約付属議定書(乙)に定める「日本政府が推薦する事業者」として設立された北サガレン石油企業組合との間に石油利権契約(コンセッション契約)を締結した[42]。そして北辰会は北サガレン石油企業組合に利権を譲渡し、1926年1月に解散した[43]。
北樺太石油利権の地図
利権契約で定められた採掘期間は45年、試掘期間は11年であった[44]。北辰会が試掘を行っていた、オハ、エハビ(ロシア語版)、ピリトゥン(ロシア語版)、ヌトウォ(ロシア語: Нутво)、チャイウォ、ヌイウォ(ロシア語: Ныйво)、ウイグレクトゥイ、カタングリ各鉱床の試掘・採掘権がコンセッション会社に供与されることとなった[45]。鉱区は約500メートル四方の正方形のマス目に分割され、日ソの自国鉱区同士が隣接しないよう市松模様状に配分された[2][46]。
1927年2月に追加協定を締結し、11ヶ所の試掘地域(北オハ(ロシア語: Северная Оха。50平方ヴェルスタ、以下単位同)、エハビ(100)、クイドゥイラニ(ロシア語: Кыдыланьи。50)、ポロマイ(ロシア語: Поромай。100)、北ボアタシン(25)、南ボアタシン(75)、チェルメニ・ダギ(200)、カタングリ(100)、メンゲ・コンギ(100)、チャクレ・ナンピ・チャムグ(100)、ヴェングリ・ボリシャヤフジ(100))の境界が定められた[47]。
北樺太石油の沿革
会社設立
日本政府は北樺太利権の獲得を受けて、コンセッション会社に関する規定を勅令によって定めるとした、「条約ニ基ク外国トノ利権契約ニヨリ外国ニオイテ事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国会社ニ関スル法律(1925年3月31日法律第37号)」を制定[48]。次いで1926年(大正15年)3月5日勅令第9号で当該規定を定めた[49]。これらに基づき「北樺太石油株式会社」が設立された[50]。中里は台湾予備油田と同様に海軍省が所管することを期待し、海軍省も半官半民の特殊会社とすることを望んでいたが、日本国内およびソ連ともにそれを許さず、商工省所管の純民間会社として設立されることとなった[51]。北樺太石油は同年6月2日に商工省の許可が下り、同月7日に設立総会を開催。資本金は北辰会、発起人、一般公募とほぼ三等分で1,000万円(うち設立時の払込400万円)を募ったが人気を博し、予定株数の11倍の応募を集め[52]、設立時点の株主数は3,655名であった[1]。また株式は東京株式取引所に上場された[53]。
経営陣には社長の中里のほか、取締役に財界から橋本圭三郎、林幾太郎(大倉鉱業)、押川方義、牧田環(三井鉱山)、松方幸次郎、斎藤浩介(久原鉱業)、島村金次郎(三菱合資会社)、末延道成らが就任した[24][54]。設立後、会社幹部および労働者400名余りが北樺太に向かい、オハ油田で事業を開始[55]。北樺太石油は北辰会の資産を受け継いだことから、すぐに生産活動を軌道に乗せた[56]。
事業体制
オハ製油所
北樺太石油は東京に本社を置き、オハに北樺太鉱業所を、その他の試掘・採掘地に支所を置いた[57]。
オハでは鉱場から樺太東海岸まで鉄道を敷設。東海岸には港がないため、海軍の支援を受けて、船舶に直接送油する1キロメートル沖合までの海底パイプラインおよび係留施設を整備した[55]。そして、1927年(昭和2年)以降、オハ油田と海岸一帯に石油タンクを設置し、1930年(昭和5年)には貯油能力が20万トンとなった[55]。また、北樺太は結氷と波浪のため6月下旬から10月末までしか荷役を行うことができない中、物資を社船「オハ丸(1,450トン)」や5,000-6,000トンの用船数隻により日本国内から輸送。オハと各支所間は75トンの発動船「チャイオ丸」で連絡した[58]。
原油は海軍の特務艦により日本に運ばれ[59][注 6]、1931年度で9割以上が海軍へ、その他は日本石油、三井物産などに販売された[41]。
労働者
コンセッション契約では、労働者の雇用比率をソ連市民75パーセント、外国人25パーセントと定めており[60]、ソ連政府は労働者の大半をソ連領内で調達することを求めていた[61]。労働者は北樺太石油がソ連側に必要人数を申請し、ソ連側が提供可能人数を北樺太石油に伝達する。ソ連市民またはソ連国内に住む外国人で必要人数を賄えない場合、北樺太石油は任意に日本人を含む外国人を採用することができた[62]。しかし、1920年代後半から30年代にかけソ連国内で工業が成長し労働者の需要が増えたこと、およびソ連の組織や制度の制約から、労働者の確保は困難を極めた[61]。なお、1933年の従業員数は、夏季が日本人1,569名、ソ連人1,494名の計3,063名、冬季が日本人791名、ソ連人963名の計1,754名であった[63]。
ソ連国内の外国企業もソ連の労働法の適用を受けることとなっており、1925年3月にはオハでも労働法が施行された[64]。同年4月に少数のソ連人により労働組合が結成されたが、日本人および日本語が使える朝鮮人は組合に加入しなかった[64]。毎年労働組合と団体協約を結ぶ必要があったが、改定の度にソ連から給料の引き上げや福利厚生の向上など事業の負担となる条件が要求されたため、交渉は毎回難航し会社の負担は増大する一方であった[65]。
労働者の住宅は北樺太石油が無償で提供する義務があったが、その面積も争点となった。1935年時点でソ連人労働者の住宅は日本人労働者の住宅の半分の面積しかなく[注 7]、組合の要求を強める要因となっていた[67]。
北樺太石油は経営を圧迫するソ連国籍労働者を抑制するため、厳正な試験を行い採用を減らそうとした[68]。ソ連は不採用労働者に樺太までの旅費および赴任手当を支払っており、不採用者が増えることが経済的負担となるため、1936年に北樺太石油による採用試験は廃止された[69]。
一方、日本人労働者は石油採掘が進んでいた新潟や秋田、乗船地に近い函館や青森から集められた。鉱夫が大部分であり、常勤労働者は長屋の大部屋に、季節労働者はテントやバラックに住んだ[70]。現地ではソ連による宣伝活動も積極的に行われたが、共産主義思想に染まった者は累計4-5千人の労働者のうち5、6人に過ぎなかった[71]。
北樺太は物資を自給自足できないため、北樺太石油が従業員に食料や衣服を提供する義務があった。食料品では、肉をアルゼンチンやオーストラリアから輸入し、缶詰もあらゆる物があるなど、日本本土にない高級品も豊富にあった[72]。日本人社員は普通、2年間を樺太で越冬し1年間東京に帰るローテーションで、2年越冬すると2千円位を稼げ、樺太成金と言われた[73]。
ソ連側の鉱区開発
戦前の北樺太における日ソ両国の石油井
北樺太石油はソ連側の鉱区についても開発を委任するよう働きかけた[74]。しかし、日本側の順調な立ち上がりを見て、ソ連も自国鉱区開発のため、1928年8月に「トラスト・サガレンネフチ(サガレン石油トラスト、ロシア語: Трест <Сахалиннефть>。以下「トラスト」)」を設立した[75]。ソ連は日本から採油機器を購入の上、自己生産の原油を日本へ輸出することを希望し、1928年(昭和3年)9月に原油売買契約を締結。これに基づき1929年(昭和4年)からトラスト産原油が輸入され、最盛期には輸入量が年間10万トンを超えた。1928年から1932年にかけての輸入量は約30万トンで、さらに、バクー産石油の独占販売権も獲得した[76]。
しかし、ソ連がハバロフスクに製油所を建設し独自の精製能力を手に入れたことや日ソ関係の悪化から、1937年(昭和12年)を最後にトラストからの購入は終了した[77]。
なお、日本が探鉱で石油の埋蔵を確認したにもかかわずソ連が生産を認めなかったエハビ油田では、トラストだけが生産を行った[2]。エハビ油田は、オハ油田の生産が落ち込む一方で増産を続け、1945年には北樺太における採油量の7割を占める51万トンを生産するに至った[78]。そして戦後さらに生産が伸び、1988年には年間260万トン、累計生産量が1億トンに達した[79]。
採油能力の低下と試掘期限延長
石油会社は事業継続のため、新たな油田開発を行い採油能力の向上を図る必要がある。しかし北樺太石油では、株主に高配当を約束していたこともあり、経費がかかる一方で短期的な利益を生まない試掘を軽視。創業から1930年度までに試掘を行ったのは、ヌトウォ、カタングリ、北オハ、ポロマイの4区域だけであった[80]。コンセッション終了期限に全資産をソ連に引き渡すことになっていたため、会社の財産を担保に資金調達することができず、当初は補助金も無かったため増資によるしかなかった[81]。1931年(昭和6年)に資本金を2,000万円へ増資するとともに、ヌトウォ、カタングリ鉱床の開発を中止して試掘を強化。日本政府からは1932年に10万円、1933年に28万4千円などと試掘助成金が給付された。しかし、1936年度までの試掘作業の支出1,336万円に対し、試掘助成金は380万円にとどまり全く足りなかった[82]。この結果、1930年代前半をピークに経営は下降線をたどり、年8パーセント配当を維持できなくなり、役員報酬も減額を余儀なくされた[81]。
左近司政三
1935年7月に社長就任した左近司政三は、1936年以降、試掘重視から採掘重視へ経営方針を転換。オハ油田の開発と並んで、北オハ、カタングリ鉱床の開発を進めた[83]。しかしオハ油田の採油量が減少する一方で、北オハ鉱床の採油量は微増にとどまりオハ油田の減産を補うには至らなかった[84]。またカタングリ鉱床は、1937年に申請した海底パイプラインの建設をソ連が許可しないなど事業を妨害したことにより、1940年には撤退を余儀なくされた[85]。
試掘期間は1925年から1936年(昭和11年)までであったが、実際に試掘に着手したのが1928年と3年間を無為に過ごしたことから、北樺太石油は早くも1929年にはソ連へ期間延長を求めた。しかしソ連はまだ試掘期間が残っていると主張し、交渉は難航。1936年に左近司社長がソ連へ行き交渉した結果、ソ連人労働者の福利向上等を交換条件に試掘期間が5年間延長された[86]。これを受けて、北樺太石油は未払込の増資金の徴収や政府保証債の発行、政府補助金により総額900万円の試掘計画を立てた。ところが同年11月に日独防共協定が締結されると、ソ連からの圧力が増していった[87]。この結果、1937年にはポロマイ、クイドゥイラニ、チャイウォ、コンギ支所を閉鎖[88]。試掘が進まない状況から日本側は試掘期限の再延長を求めたが、1936年の延長時に付属文書で再延長は行わないと約していたためソ連は認めなかった[89]。
ソ連の経営妨害
第一次五カ年計画で国力を増したソ連は外国資本の排除にかかり、北樺太石油にも圧力をかけるようになった[90]。
北樺太のコンセッション企業はソ連の鉱山監督官、労働監督官、技術監督官に監督されていた。ソ連の国内法やコンセッション契約の違反を判断する監督官の権限は強く、監督官の命令で作業が中止されたり、時にはモスクワでの交渉を余儀なくされることが頻繁に発生した。また、監督官によって対応は異なり、北樺太石油に厳しくトラストには甘いといった不公平な対応が頻繁に行われた[91]。
ソ連は様々な妨害を行い、以下のような状況であった。
事業計画や物資輸入計画、労働者雇用計画、原油搬出計画などの認可を遅らせたり縮小・却下させ、予定作業を妨害[92]。
現地事情を考慮せず、大規模な技術安全規定、衛生火防規定などを杓子定規に適用し、命令・要求を頻発[92]。
社員の入国を妨害。左近司政三社長も現地視察を拒否された[93]。
社員を些細な法規違反で裁判にかけ、過酷な刑罰を適用[92]。中にはスパイ容疑をかけられ、2年半の実刑を受けた者もいた[94]。
1938年には赤字に転落し、政府からの補助金で埋め合わせた[95]。
これらの圧力に対して北樺太石油および駐ソ大使が抗議を行い、また国内でも外務省が世論に訴えた[92]。そして1939年(昭和14年)2月には衆議院で日本政府に対策を講じるよう求める「対ソ権益確保に関する決議」がなされ[96]、同年6月末から9月末まで[97]、海軍も軽巡洋艦夕張のほか駆逐艦数隻がオハ沖で示威行動を行い権益保護の姿勢を見せた[98]。しかし同年には団体契約交渉が難航、労働組合の要求の大半を受け入れて11月に調印したが、冬季労働者の雇用申請期限に間に合わず、エハビ、カタングリでの越冬経営が不可能になった[99]。
北樺太利権の解消と会社消滅
1941年(昭和16年)に締結された日ソ中立条約の交渉過程で、ソ連は北樺太の利権解消を強く主張し日本と対立した。1940年(昭和15年)11月、ヴャチェスラフ・モロトフ外務人民委員は建川美次駐ソ大使に対し中立条約締結と利権解消を提案。これに対し日本政府は利権解消を拒否し、逆に日本への北樺太売却を打診したが相手にされなかった[100]。1941年4月に行われた松岡洋右外務大臣とモロトフの会談で再度議論されたが、最終的には利権解消で決着した[101]。中立条約締結時に取り交わされた松岡とモロトフの半公信に「北樺太利権の整理問題は数か月以内に解決するよう和解及び相互融和の精神をもって努力する」と盛り込まれた[102]。松岡は北樺太利権の解消に積極的ではなかったが、利権があまり役立たないものとなっていたため解消を決め、他の閣僚には日本帰国後に説得するとして半公信を渡した[103]。しかし半公信が非公表であったこともあり、日本政府はこの問題を放置した[104]。
1941年6月に独ソ戦が始まるとソ連の北樺太石油への圧力は一時的に緩和したが、同年12月に期限を迎えていた試掘期間の再延長は拒否された[105]。1942年(昭和17年)末に東部戦線の戦況がソ連有利に転じると再び圧力が増すようになる[106]。そしてソ連は利権返還の約束を果たさなければ日ソ中立条約の破棄もやむを得ないと主張してきた[107]。このため、1943年(昭和18年)になると日本政府はソ連との緊張を緩和するための交渉材料として、佐藤尚武駐ソ大使の建言を受けて、6月19日の大本営政府連絡会議で北樺太利権の有償譲渡を決定した[108]。加えて、7月に北樺太へ食糧や生活物資を輸送していた用船が金華山沖で撃沈され事業継続困難になった[109]ことから、北樺太石油は8月1日に事業停止に着手、11月に留守番ほか社員約100名を残して北樺太から撤退した[107]。
日ソ両国は1944年(昭和19年)3月30日、「北樺太の石油および石炭利権に関する移譲議定書」を締結。ソ連へ譲渡される資産の帳簿価格は2,174万円であったが、ソ連が請求してきた契約や法規違反の代償金と相殺され、当時の約400万円[110]にあたる、わずか500万ルーブルの対価で北樺太の利権を放棄した[111][107][注 8]。ただしソ連は「現在の戦争終了時から[注 9]」5年間、毎年5万トンを日本へ供給することが定められた[111]。これにより事業を失った北樺太石油は政府の斡旋を受けて、国内石油鉱業一元化のために設立された国策企業である帝国石油に7月1日に吸収合併されて消滅した[109]。
なお北樺太石油は、太平洋戦争開始後、国内の石油技術者を南方へ送ったため人手不足となった帝国石油の八森油田(現在の秋田県八峰町にあった)を1942年12月から経営受託していた。1944年時点で八森油田の103名を含め従業員は904名であったが、一部の社員は「北樺太石油南進隊」(後述)として海軍に徴用され、残りは帝国石油に移籍した[114]。
北樺太石油南進隊
北樺太石油の位置(インドネシア内)北樺太石油
クラモノ油田の位置
太平洋戦争中、南方で石油資源の獲得を進めていた海軍は、ニューギニア島西部にあるクラモノ(Klamono)油田の開発を行うこととし、第101燃料廠(本部・ボルネオ島)の下に調査隊を編成したが、燃料掘削と採油の技術者が不足していた。こうした中、北樺太石油はソ連の圧力により多くの社員が北樺太に渡航できず本土に留まっていたことから、社員315名[注 10]を軍属として徴用することで海軍と合意し、常務取締役・片山清次(予備役海軍少将)[注 11]引率の下、隊を結成した[117]。
1944年2月1日に佐世保港を出発したが、当初は海軍の調査隊と合流することは極秘となっていたため、「北樺太石油南進隊」と呼称された[117]。2月17日にスラバヤに到着。ここで二隊に分かれ、先発隊がニューギニア、残りはボルネオへ向かった[116]。先発隊はアンボンを経てクラモノ油田で調査隊に合流するが、うち89名はビアク島の陣地構築作業に回された。彼らは1944年5月に始まったビアク島の戦いに巻き込まれ三々五々脱出を図ったが、生還したのは18名のみであった。ニューギニアの隊員も連合軍の進攻のため6月には作業を中止しボルネオへ撤退[118]。当初の任務は完了したものの多くの隊員は帰国できず燃料廠の各地の油田に配属された[119]。1945年(昭和20年)3月に40名がシンガポールから帰国の途についたが、乗船・阿波丸がアメリカ潜水艦の攻撃を受け沈没、全員死亡した(阿波丸事件)[120]。最終的に他の死者を含め315名中160名が戦病死し[120]、生存者の大部分は帝国石油に復職した[121]。
経営陣
社長、常務には主に海軍出身者が就任し、その他、日本石油等から取締役を出していた[122]。
歴代社長
代 社長 任期 備考
1 中里重次 1926年6月7日 - 1935年7月19日 海軍中将
2 左近司政三 1935年7月19日 - 1941年10月6日 海軍中将
3 荒城二郎 1941年10月6日 - 1944年6月30日 海軍中将
業績
以下の出典は(村上隆 2004, pp. 144?145)。
年度 生産・出荷(トン) 営業成績(万円)
オハ カタングリ 収入 支出 純益 配当
採油 ソ連から購入 日本へ搬出 採油 日本へ搬出
1926 33,037 20,600 98 90 5
1927 77,227 44,900 216 166 38 32
1928 121,356 90,300 10 358 255 59 45
1929 186,641 27,700 131,500 420 501 354 82 61
1930 192,145 37,300 199,000 1,230 564 376 102 77
1931 186,329 112,500 272,800 1,820 505 350 89 81
1932 186,073 135,000 313,600 1,160 530 380 80 75
1933 193,355 124,700 313,600 2,400 563 398 87 73
1934 161,849 123,200 241,500 3,000 508 373 30
1935 163,473 40,000 174,600 4,190 584 400 77 53
1936 155,183 40,000 167,000 24,960 643 407 127 114
1937 130,369 100,000 217,300 20,220 593 369 94 80
1938 101,676 127,200 25,600 34,000 783 630 36 80
1939 84,894 51,400 9,530 4,060 981 791 84 80
1940 57,358 45,300 0 925 746 85 80
1941 43,709 15,600 8,060 950 762 85 80
1942 51,578 1,109 935 85 80
1943 17,049 9,500 844 621 87 80
1944 17,300
脚注
大東亜戦争(太平洋戦争)日本の英雄
11.沖縄県民斯(か)ク戦ヘリ
県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ 賜ランコトヲ
12.中川州男とペリリュー島の戦い~バンザイ突撃の禁止、 相次ぐ御嘉賞と将兵の奮闘
13.硫黄島の戦い(いおうとうのたたかい、いおうじまのたたかい[注 1]、Battle of Iwo Jima, 1945年2月19日 - 1945年3月26日)は、第二次世界大戦末期に東京都硫黄島村に属する小笠原諸島の硫黄島において日本軍とアメリカ軍との間で行われた戦いである。アメリカ軍側の作戦名はデタッチメント作戦(Operation Detachment)。
14.占守島…日本を分断から救った男たち
#樋口季一郎日本領千島列島の北東端・占守島(しゅむしゅとう)に不法侵攻してきたソ連軍に対し、日本軍が祖国を守るべく戦った「占守島の戦い」です。
15.妻を後部座席に乗せソ連軍へ特攻~書評『妻と飛んだ特攻兵』
1. 9軍神 開戦劈頭の大戦果として,特殊潜航艇で真珠湾攻撃
2.淵田 美津雄 真珠湾奇襲 攻撃隊長
3.空の神兵(そらのしんぺい)とは、大日本帝国陸軍・海軍の落下傘部隊(空挺部隊・挺進部隊)、落下傘兵
3.坂井三郎 ガダルカナル上空で被弾し片目を失いながら1000kM操縦しラバウルに帰還したエースパイロット
4.
マレー沖海戦
【日本海軍】
■指揮官
「松永貞市少将」
5.加藤隼戦闘隊(かとうはやぶさせんとうたい、)とは、大東亜戦争初期に活躍した加藤建夫陸軍中佐
6.
ラバウル航空隊(ラバウルこうくうたい)とは、第二次世界大戦時、ニューブリテン島(現在のパプアニューギニア)のラバウル基地に集結してこの空域に展開して戦闘に参加した、日本海軍・陸軍の各航空隊(航空部隊)の総称である。
7.ガダルカナル島撤収作戦(がだるかなるとうてっしゅうさくせん)は第二次世界大戦中に行われた日本軍の撤退作戦。作戦呼称は「ケ号作戦」。由来は捲土重来(けんどちょうらい)による[要出典]。
8.キスカ島撤退作戦(キスカとうてったいさくせん)は、第二次世界大戦中の1943年(昭和18年)5月27日から7月29日に行われた、日本軍のキスカ島(アメリカ合衆国アラスカ準州アリューシャン列島内)からの守備隊撤収作戦のことである。
9.アッツ島玉砕
アッツ島の戦い(アッツとうのたたかい、Battle of Attu)は、第二次世界大戦中の1943年(昭和18年)5月12日にアメリカ合衆国アラスカ準州アリューシャン列島で、アメリカ軍のアッツ島上陸によって開始された日本軍とアメリカ軍との戦闘である[1]。
10.拉孟・騰越の戦い(らもう・とうえつのたたかい)は、1944年6月2日から1944年9月14日まで中国・雲南省とビルマ(現ミャンマー)との国境付近にある拉孟(保山市竜陵県)・騰越(同市騰衝市)地区で行われた、日本軍と中国国民党軍・アメリカ軍(雲南遠征軍)の陸上戦闘のことを言う。
9月9日、中華民国総統の蒋介石が、部下将兵に与えた訓示である。これこそは、敵側が如何に拉孟守備隊の勇戦に苦しめられたかを明確に示す証拠であり、蒋介石から拉孟の将兵に手向けた逆感状とも言えるであろう。
「松山陣地(拉孟陣地と同義)は9月7日、我が軍において攻占するところとなり、欣快に堪えず。(中略)戦局の全般は我に有利に進展しつつあるも、前途なお遼遠なり。(中略)
諸子はビルマの日本軍を模範とせよ。拉孟において、騰越において、ミートキーナにおいて、日本軍の発揚せる忠勇と猛闘を省みれば、我が軍の及ばざること甚だ遠し」
11.中川州男とペリリュー島の戦い~バンザイ突撃の禁止、 相次ぐ御嘉賞と将兵の奮闘
12.硫黄島の戦い(いおうとうのたたかい、いおうじまのたたかい[注 1]、Battle of Iwo Jima, 1945年2月19日 - 1945年3月26日)は、第二次世界大戦末期に東京都硫黄島村に属する小笠原諸島の硫黄島において日本軍とアメリカ軍との間で行われた戦いである。アメリカ軍側の作戦名はデタッチメント作戦(Operation Detachment)。
。
拉孟・騰越の戦い(らもう・とうえつのたたかい)は、1944年6月2日から1944年9月14日まで中国・雲南省とビルマ(現ミャンマー)との国境付近にある拉孟(保山市竜陵県)・騰越(同市騰衝市)地区で行われた、日本軍と中国国民党軍・アメリカ軍(雲南遠征軍)の陸上戦闘のことを言う。
すでに南部を占領していた日本の部隊は援?ルートの遮断のために派遣された小規模なもので、進出した当初の1942年頃は中国軍に対して優位に立っていたが、援?ルート遮断後もアメリカ軍の空輸によって中国軍への支援が継続されたため、連合軍の指導によって近代的な装備を身につけた中国軍が1944年より反撃に転じ、日本軍は補給路を断たれ孤立し、拉孟守備隊および騰越守備隊は最終的に玉砕した。硫黄島などの孤島において玉砕したケースは多いが、この戦いは大陸において玉砕した珍しいケースとして知られる。しかし、中国軍も陣地に立てこもる日本軍の防御戦闘により部隊比では日本より死傷者を出した。
経緯
拉孟、騰越の戦い
https://blog.goo.ne.jp/kitasan999_555/e/2129583bcd02de72e3d323057bd6974f
民の琴線に触れる戦いがある。特に10倍を超す敵に囲まれ最後の一兵まで戦った場合には、その記憶は千年の時を超す。ユダヤ人は2千年前(紀元70~73年)のマサダの戦いを、団結の象徴として昨年のことのように話す。
紀元66年のユダヤ戦争。ローマ帝国からの独立を目指して立ち上がったユダヤ人は、エルサレムで敗れ追い詰められて967人の女子供を含む集団が、急峻なマサダの砦に立て籠もった。1万5千人のローマ軍兵士が砦のある丘を包囲したが、周囲は断崖絶壁で唯一の登攀路を塞がれて手が出せない。そこでローマ軍は2年の歳月をかけて大規模な土木工事を行い、角となる木材と大量の土砂を運んで絶壁の一方向を埋め立てた。古代の土木技術は侮りがたい。ついに絶壁にゆるやかなスロープを作り出した。満を持したローマ軍が砦に突入するが、予想された抵抗はなかった。中にいたユダヤ人は集団自殺を遂げていたのだ。生き残ったのは、穴に隠れていた2人の女と5人の子供だけだった。
アメリカ人にとって心を熱くする戦いはアラモ砦の防衛戦だろう。こちらは1836年2/23~3/6の13日間包囲されたが、総攻撃により一日で砦は陥落し、守備隊は全滅した。砦に籠ったのはテキサス分離独立派、当時のテキサスはメキシコ領だった。トラヴィス隊長のもと、西部で名高いジム・ボウイとデイヴィー・クロケットが参戦し183~250人の男達が戦った。
攻めるのはサンタ・アナ率いるメキシコ共和国軍4,5千人だが、総攻撃の時には1,600人で攻め3~400人のメキシコ兵が戦死した。アラモ砦の犠牲により貴重な時を稼ぎ結束したテキサス独立軍は、「リメンバー・アラモ」を合言葉にメキシコ軍を打ち破りサンタ・アナを捕虜にする。
日本軍は太平洋の島々や沖縄で米軍と死闘を繰り広げるが、自分の琴線に触れる戦いはビルマと中国雲南省の国境付近で行われた。拉孟(ラモー)・騰越(トウエツ)の戦いには心を揺さぶられる。平静ではいられず、心が高ぶるのだ。拉孟は怒川の西岸、恵通橋を見下ろす海抜2,000mの山上にある廃村を基にした陣地で、周囲を山と渓谷に囲まれ西方のみが龍陵に通じている。四季の変化に富み特に秋は美しい所だそうだ。一方騰越は、最前線の拉孟から北東に60km、平野の中央にある人口4万の城郭都市で、東は山脈を縦走して保山、昆明へと続く。
日本軍は何故このような山奥に攻め入り、陣地を築いたのか。それは連合軍の援蒋ルートを断つのが目的である。太平洋戦争が始まる前の5年間、日本と中国は激しく戦っていた。個々の会戦では常に日本軍が勝利を収めていたが、倒しても倒しても新手の中国軍が現れる。前線が進むにつれ、占領地である後方の物資集積所、小規模駐屯地、鉄道や輸送隊等が襲撃される。後方の防衛を固めようとすると、守備に限りなく人員が必要になる。前線は先に進み占領地は増え、守備部隊を増やしてもその中で手薄な所や輸送隊が襲われる。日本は徴兵を進めついに100万の兵力を中国に送り込んだ。
南方へ行き、太平洋戦争で米英蘭軍と戦った日本軍は、中国に張り付いた兵力の1/4~1/5に過ぎない。日本陸軍は8年間、もしくはそれ以上の期間中国に居続けた。その日本軍と対峙していたのが200万を超す中国軍である。蒋介石を負かせてはならない。100万の戦慣れした日本兵を他の戦場へ向かわせたら恐ろしいことになる。連合軍、特に米国は太平洋戦争以前、ビルマのラングーンに大量の軍需物資を陸揚げしてビルマから中国、雲南省を経由して重慶にいる蒋介石のもとに送った。この援蒋ルートを断ち切るのが日本軍の狙いだった。アメリカは陸路が封鎖された後は、ヒマラヤ超えの危険な空輸で蒋を支えた。今でもヒマラヤ山脈から中国の奥地には、大戦中の大型輸送機の残骸が散らばっているはずだ。
蒋介石の元にはアメリカから派遣されたジョセフ・スティルウェル大将がいて、米軍の援助物資を装備した中国軍を訓練していた。近代装備を持ち訓練された新編師団(雲南遠征軍)が満を持してビルマに進入してきた。中国人指揮官、衛立煌の率いる20万人で、装備は日本軍よりも遥かに近代的だ。英印軍だけでも手一杯の所に新規の20万とは。最前線基地の拉孟はたちまち包囲された。
拉孟守備隊は当初2,800名の兵力だったが、指揮官の松山大佐は命を受け、兵を割いて出撃し侵入してきた雲南軍の一部を撃退した。その後松山隊はミイトキーナ南方に降下した英軍空挺部隊の掃討等に転戦し、6月5日騰越に入った。拉孟に残された守備隊は1,280名で、その内300名は負傷兵であった。拉孟を包囲した中国軍は4万8千名で、残りの雲南軍は騰越、龍陵、平戛に向かった。
1944年6月2日午後、雲南遠征軍の砲撃が始まった。この日から9月7日に陣地が陥落するまでの66日間、拉孟守備隊は攻撃を再三防ぎ、敵二個師団を壊滅させ戦死4千、負傷3,774人の損害を与えた。雲南軍司令官衛立煌大将は、日本軍の強さに舌を巻きこう語った。『火砲の力を入れると、こちらは日本軍の十倍以上の戦力である。それが千五百そこそこの日本軍に軽くあしらわれてしまったのである。何という強い日本兵なのだ。』
敵将があきれるほどの勇戦を指揮した金光少佐(死後大佐)は小学校しか出ていない。貧農の子で村では神童と言われていたが、一兵卒からたたき上げ伍長、軍曹を経て幹部候補となり将校にまでなった。元が貴族社会の英国ではほぼあり得ない昇進だ。さんざん悪く言われる帝国陸軍だが、このような将校を生みだすところは素敵だ。金光少佐は常に温厚で部下思い、自ら率先して事を成すタイプで、部下からはこの人の下でなら死ねる、と慕われていた。拉孟守備隊は、限られた資材を使って陣地を複合的に設営し、死角を無くしてどこからでも十字砲火を浴びせて敵に出血を強いる構造を効果的に作り上げた。度重なる砲撃による破損は、夜間に不断に補修を行った。
6/7、雲南軍の攻撃を迎撃し、敵の将軍を戦死させた。6/14、別師団による北方からの攻撃。6/20、敵主力2個連隊が再攻撃、これを粉砕するも砲撃戦で守備隊の弾薬庫が被弾破裂した。これは大きな痛手となった。砲弾が残っていたら、雲南軍の犠牲はもっと大きかったに違いない。6月末、2年前に日本軍の急追を逃れるために自ら爆破した恵通橋を復旧。これにより雲南軍の補給物資がトラック輸送により、陸続と戦場に運び込まれた。
6/28、日本陸軍機10機飛来、上空より空中補給。その後も度々飛来。7/4~15、雲南遠征軍第2次総攻撃。ロケット砲と火炎放射器が加わり、守備隊は大きく兵を失った。残存兵力は500を切り、生き残った兵も多くは傷ついていた。守備隊の砲弾は欠乏して撃ち返すことが出来なくなった。天候は雨季に入って壕内は膝までぬかるみと化し、守備兵は脚気とマラリアに苦しめられた。
守備隊は夜になると数名づつ陣地の前面に出て、雲南軍の死体の山から武器・弾薬・食糧を拾い集めた。ビルマ方面軍は、連合軍によって新たに築かれつつある補給ルートを遮断し、同時に拉孟・騰越守備隊を救援するという「断作戦」を発令した。救援部隊を9月上旬に拉孟に送ると約束し、拉孟守備隊は希望を持ったが、実は最前線の拉孟は最初から見捨てられていた。戦略的にも無意味なインパール作戦によって、虎の子の精強な3個師団と1旅団を失い、日本軍と英印軍の戦力対比が最大1:10となり、制空権も失っていた。本土から派遣されてきた京都の師団は弱兵で役にたたない。かろうじてミートキーナ(現ミッチーナ)から一部の部隊が撤退出来たのが精一杯であった。ミートキーナから退却出来たのは10人に1人に過ぎないが、拉孟と騰越で敵を引きつけて時を稼いでくれたから全滅せずにすんだ。当初ミートキーナにも死守命令が出ていたが、わずかな兵を率いて救援に赴いた水上少将が自決をして名目的に死守命令を守り、部下を撤退させた。
7/20、第3次総攻撃。この攻撃は昆明から呼び寄せた新しい部隊によって行われ、拉孟陣地には一日当り7~8,000発の砲爆撃がなされた。攻撃部隊が陣前に肉薄して投げ込む手榴弾を、守兵が拾って投げ返す。陣内に突入してきた敵兵は、得意の白兵戦で刺し殺し殴り殺す。7/25頃には兵力は300名に減少した。砲弾は最後の一発を残して既に無く、歩兵弾薬は欠乏し食糧庫を焼かれ、8月以降は乾パン一袋を2日に食い延ばすようになった。
7/27、ビルマ方面軍司令官より、拉孟守備隊の勇戦に対し感状が届く。翌日第33軍司令官からも感状。8/2、複数ある陣地のうち、本部陣地が陥落。8/12、挺身破壊班を編成、4名1組の破壊班を7組送り出して雲南軍を奇襲。破壊班は民間人に変装して遠征軍の包囲をすり抜け、火砲5門その他を破壊し、戦利品を持って帰還。損害は戦死2名であった。この攻撃で守備隊の士気はあがった。
さて拉孟陣地に空輸に来た陸軍機だが、速力の早い一式戦・隼なので狭い陣地にピンポイントで投下するのは困難で、半分は敵の手に渡ってしまった。また地上からの砲火に加え、敵戦闘機が待ち伏せるようになって撃墜される機が出始めた。しかしちぎれんばかりに手を振る守備兵を見たパイロットは、再出撃、再々出撃を進言した。これに対し金光少佐が無線で司令部に告げた。『今日も空投を感謝す。手榴弾100発、小銃弾2,000発受領。将兵は1発1発の手榴弾に合掌して感謝し、攻め寄せる敵を粉砕しあり。』『我が飛行隊が勇敢なる低空飛行を実施し、これが為敵火を被るは、守備将兵の真に心痛に堪えざるところなり。余り無理なきようお願いす。』それを聞いた隼隊は出撃を志願したが、7月中旬になると陣地はさらに小さくなり、手を振る守備兵は負傷して包帯を巻いた負傷兵ばかりで、投下しても陣地内の日本兵にはほとんど渡らなかった。実際最後の数百名は、片手片足、失明した兵が幽鬼のように敵に立ち向かっていた。
雲南軍は、これまでの中国戦線の中国軍とは思えないほど勇敢に戦った。殺すのを一瞬ためらう程の少年兵が多かったという。しかし初陣の彼らは真っ正直に正面から戦い過ぎた。老練な日本軍の仕掛けたトラップに嵌り、犠牲を重ねた。日本軍にとっては、効果的に限られた武器で最大の効果をあげたと言える。中国軍は何度か降伏勧告を行ったが、鼻で笑われてしまった。
8月中下旬の雲南軍の攻撃は中央付近の関山陣地に集中し、地上攻撃と併せて陣地直下まで掘り進んだ坑道による地中3ヶ所からの爆破により、8/19ついに陣地を奪われた。しかし8/20夜間、なけなしの兵を集めて夜襲を敢行して奪還。翌日再び奪取されるも8/22未明、逆襲して再奪取。しかし兵力が尽き、確保を続けることは出来なかった。
9/5、決別電報を打ち、無線機を破壊し重要書類を焼却。9/6、金光少佐戦死。迫撃砲弾により腹部と大腿部を粉砕されていた。金光隊長は真鍋副官に後事を託しつぶやいた。『皆、よくやってくれた---』享年48歳。翌9/7未明、真鍋大尉、砲兵掩蓋内にて軍旗奉焼。早朝より激しい集中砲火を受け松山陣地陥落。午後真鍋大尉敵中に切り込み戦死(死後、少佐に進級)。18時全ての陣地が陥落し戦闘終結。突然戦場に静寂が広がった。
真鍋大尉の命を受け、中尉ら数名が脱出し地元民に変装して戦線を突破し、日本軍の司令部に辿りついた。将校の生還者がいたことで、拉孟守備隊の最期の様子は比較的よく分かっている。騰越では一人の生存者もいない為、戦闘の詳細が今一つ不明である。
拉孟守備隊の陥落した陣地跡に自決した15名の日本人慰安婦が横たわっていた。5名の朝鮮人慰安婦は雲南軍に投降した。降り注ぐ砲弾の雨の中で、守備隊が一番安全な場所に女達を匿っていたことが伺える。また最期の時に日本人慰安婦のお姉さんが、朝鮮人の女の子に降伏を勧めたのだろう。雲南軍は女がこの激戦の戦場にいたことに驚き、従軍看護婦として丁重に埋葬した。
拉孟には軍属によって酒保(売店)と慰安所が出来ていた。女達は攻撃が近づいた時に引き上げることも出来たのだが、何故か残留を望んだ。長い間暮らしを共にした兵隊と女達の間には、家族愛のような絆が生まれていた。戦闘の最中に、一人の兵隊がなじみの女との結婚を申し出て許可された、という話しがある。しかし勇者として名誉の戦死を遂げた兵士に較べ、名もなく闇に葬られた死を遂げた女達があわれだ。彼女達も共に戦い、弾丸を運び炊事に従事し傷ついた兵を手当てし看護し、勇敢に死を選んだのに。
金光隊長が9/5、師団司令部に送った決別電文は以下の通り。
『通信の途絶を顧慮して、予め状況を申し上げたし。---周囲の状況急迫し此までの戦況報告の如く全員弾薬食糧欠乏し。如何とも致し難く最後の時迫る。将兵一同死生を超越し命令を厳守確行、全力を揮ってよく勇戦し死守敢闘せるも、小官の指揮拙劣と無力の為御期待に沿うまで死守し得ず。まことに申し訳なし。謹みて聖寿の無窮、皇運の隆昌と兵団長閣下はじめ御一同の御武運長久を祈る。』
騰越は城郭都市で、城壁は周囲4km正方形で高さ5m、幅2m、外側は石で内側は積土で固められていた。周囲の高地からは見下ろす位置にあるため、これらの高地も防衛する必要があったが、それには最低でも3個連隊、7千名の兵が必要だ。騰越守備隊長は水上少将であったが、少将はミイトキーナ救援に向かったので、蔵重大佐以下2,800名が雲南軍49,600名を迎えうった。守備隊は全滅、雲南軍は戦死9,168名、負傷10,200名の損害を出した。
戦闘が始まる直前、師団司令部から1大隊の抽出を命ぜられた。そのため実際に騰越で戦ったのは2,800名ではなく2,025名であった。6/27、雲南遠征軍の砲撃開始。7/27、外郭陣地を放棄し城内に後退。8/13早朝、戦爆連合の24機が騰越城を空爆、その一弾が防空壕を直撃して蔵重大佐以下32名が戦死。以後太田大尉(28歳)が指揮をとった。この時点で守備兵は800名になっていた。連合軍の空爆は激しかった。
しかし騰越守備隊の凄まじい抵抗はむしろここから始まる。組織的防戦から死に物狂いの抵抗へ。空爆で崩れた城壁からなだれ込んできた5千を超す雲南軍と壮絶な市街戦を繰り広げる。昼間奪われた地域は夜襲で奪い返す。8/21、残存640名。9/1~5、残存350以下。9/7、追い詰められた守備隊は太田大尉以下70名。9/11、守備隊の弾薬、手榴弾が尽きる。9/12、最後の無電。
9/13、太田大尉の指揮下、生き残った数十名が軍刀と銃剣により敵陣地に突入して全員戦死。太田大尉の決別電は以下の通り。
『現状ヨリスルニ、一週間以内ノ持久ハ困難ナルヲ以テ、兵団ノ状況ニ依リテハ、十三日、連隊長ノ命日ヲ期シ、最後ノ突撃ヲ敢行シ、怒江作戦以来ノ鬱憤ヲ晴ラシ、武人ノ最後ヲ飾ラントス。敵火砲ノ絶対火制下ニアリテ、敵ノ傍若無人ヲ甘受スルニ忍ビズ、将兵ノ心情ヲ諒トセラレタシ。』
9月9日、敵将蒋介石は、雲南軍司令部に与えた訓示の中で次のように述べた。
『戦局の全般は我に有利に進展しつつあるも、前途なお遼遠なり。我が将校以下は、日本軍の拉孟守備隊、騰越守備隊あるいはミートキーナ守備隊が孤軍奮闘最後の一兵に至るまで命令を全うしある現状を範とすべし。日本軍の発揚せる忠勇と猛闘を省みれば、我が軍の及ばざること甚だ遠し。』
これが有名な蒋介石の逆感状である。日本軍の出す美辞麗句を並べた陳腐な感状に較べ、敵から範とすべしと言わしめたのだ。これ程価値のある(逆)感状はない。蒋介石は毀誉褒貶の多い人物だが、敵の勇気に感動する度量のある人だった。このことだけでも結構好きだな。拉孟・騰越の勇者がもし生きていてこのことを聞いたなら、一番うれしい一言だったに違いない。
。
もう一つは、9月9日、中華民国総統の蒋介石が、部下将兵に与えた訓示である。これこそは、敵側が如何に拉孟守備隊の勇戦に苦しめられたかを明確に示す証拠であり、蒋介石から拉孟の将兵に手向けた逆感状とも言えるであろう。
「松山陣地(拉孟陣地と同義)は9月7日、我が軍において攻占するところとなり、欣快に堪えず。(中略)戦局の全般は我に有利に進展しつつあるも、前途なお遼遠なり。(中略)
諸子はビルマの日本軍を模範とせよ。拉孟において、騰越において、ミートキーナにおいて、日本軍の発揚せる忠勇と猛闘を省みれば、我が軍の及ばざること甚だ遠し」
11.中川州男とペリリュー島の戦い~バンザイ突撃の禁止、 相次ぐ御嘉賞と将兵の奮闘
https://shuchi.php.co.jp/rekishikaido/detail/7798
Twitter
シェア
LINEで送る
linkedin
2020年07月27日 公開
2020年08月05日 更新
早坂隆(ノンフィクション作家)
ペリリュー島に残る大砲
南洋の島、ペリリュー島。
約1万の日本軍守備隊に対し、米軍の総兵力はおよそ4万2千人。
その中核は、米軍最強と謳われた第一海兵師団である。
彼我の戦力差は明らかであったが、日本軍は島じゅうに張り巡らせた地下壕を駆使し、徹底抗戦を試みる。
驚異的な奮闘を指揮したのが、中川州男(なかがわくにお)大佐であった。
※本稿は、歴史街道編集部編『太平洋戦争の名将たち』より、一部を抜粋編集したものです。
パラオの発展に尽力した日本
西太平洋上に位置するパラオ共和国は、珊瑚礁に囲まれた美しい島嶼国家である。しかし、この「楽園」のような小さな島々にも苦渋の歴史がある。19世紀後半以降、パラオはスペインとドイツに相次いで植民地とされ、島民たちは搾取と愚民化政策の対象とされた。
転機となったのは第一次世界大戦後である。大正9年(1920)、国際連盟の正式な決定によって、パラオは日本の委任統治領となった。以降、日本はインフラ整備や産業振興、学校制度の導入など、様々な政策を実行。その結果、島民の生活レベルや識字率は大きく向上した。
しかし、大東亜戦争(太平洋戦争)が始まると、パラオは米軍の標的となった。フィリピン方面への攻撃拠点を求める米軍にとって、パラオ南端のペリリュー島にある大規模な飛行場は格好の存在であった。昭和19年(1944)、米軍はペリリュー島への上陸計画を策定した。
これに対して日本軍は、ペリリュー島におけるそれまでの防備を根本から見直し、強力な迎撃態勢の構築を急いだ。
その指揮をとった現地司令官が、歩兵第二連隊長・中川州男大佐である。
中川は明治31年(1898)1月23日、熊本県の玉名郡で生まれた。一家は累代の熊本藩士という由緒ある家系だったが、明治になって武士の時代が終焉するとその生活は一変。中川の祖父や父は、学校や塾で国学や漢学などを教える教育者に転じた。ちなみに中川の父親である文次郎は、西郷隆盛率いる薩摩軍と共に戦った熊本隊の一員として西南戦争に参戦し、新政府軍と干戈を交えた経歴を持つ。文次郎はこの戦闘に敗れた後に、教育を生業とする道を歩むようになった。
そんな家風の影響であろう、中川の二人の兄も教育畑へと進んでいる。すなわち、中川家とは筋金入りの「教育一家」であった。中川も世が世なら素晴らしい教育者になったのではないか。
そのような環境で生まれ育った中川は、文武両道を地で行くような青年となった。口数は少ないが正義感が強く、純粋な性格であったと伝わる。地元の名門・玉名中学校(現・熊本県立玉名高等学校)に進学した中川は剣道部に所属し、多くの学友たちと共に汗を流した。学科では漢学が得意であったという。
そんな中川が卒業後に選んだのは、教師ではなく陸軍将校への道であった。成績優秀だった中川は、「陸軍を担う将校」を育成するための専門機関である陸軍士官学校に合格。熊本を出て上京し、同校で学ぶことになった。時は第一次世界大戦下であり、日本も国防の重要性が改めて意識された時期であった。また、元藩士といえども当時の中川家は経済的に困窮しており、そんな家族の生活を憂う心境もあって、学費のかからない同校に進んだとも言われている。同校では軍事学はもちろん、幅広い高等教育が実施された。
大正7年(1918)、同校を卒業した中川は、福岡県久留米市の歩兵第四十八連隊で本格的な軍隊生活に入った。大いなる希望を持って入営した中川であったが、その後は学校の配属将校といった「閑職」に回された時期も長かった。エリート校である陸軍士官学校の卒業者とは言え、中川の軍人人生は順風満帆だったわけではない。
そんな中川の生涯において大きな分岐点となったのが日中戦争(支那事変)であった。中川は第二十師団歩兵第七十九連隊の大隊長として華北戦線に出征。この時の一連の戦闘において中川は冷静かつ巧みな指導力を発揮し、上層部から高い評価を得た。その結果、中川は連隊長の推薦によって、陸軍大学校専科への進学を許されたのである。
こうした経歴を見ると、中川という軍人は「挫折を知る」「現場からのたたき上げ」であったと言える。
陸大専科で学んだ中川はその後、独立混成第五旅団参謀などを経て、栄職である歩兵第二連隊長を拝命。茨城県の水戸を編成地とする同連隊は当時、「陸軍の精鋭」と呼ばれた部隊であった。
同連隊は満洲北端の嫩江(のんこう)に「対ソ戦の備え」として駐屯していた。中川も嫩江で一年ほど過ごしたが、昭和19年(1944)3月、南方への転出が決まった。悪化の一途を辿る太平洋戦線において、米軍と雌雄を決するためである。日本軍は虎の子の「切り札」を、満洲から太平洋へ振り分けたことになる。
中川は「二度と戻れない」という覚悟をもって、南洋へと向かった。
歩兵第二連隊の行き先は、パラオ・ペリリュー島であった。
11.硫黄島の戦い(いおうとうのたたかい、いおうじまのたたかい[注 1]、Battle of Iwo Jima, 1945年2月19日 - 栗林忠道陸軍中将
1945年3月26日)は、第二次世界大戦末期に東京都硫黄島村に属する小笠原諸島の硫黄島において日本軍とアメリカ軍との間で行われた戦いである。アメリカ軍側の作戦名はデタッチメント作戦(Operation Detachment)。
概要
硫黄島遠景(2007年)。
『硫黄島の星条旗』をかたどった合衆国海兵隊戦争記念碑
1944年8月時点での連合軍の戦略では、日本本土侵攻の準備段階として台湾に進攻する計画であった[10]。台湾を拠点とした後に、中国大陸あるいは沖縄のいずれかへ進撃することが予定された。台湾の攻略作戦については「コーズウェイ作戦」 (土手道作戦) としてに具体的な検討が進められたが、その後に陸海軍内で議論があり、1944年10月にはアメリカ統合参謀本部が台湾攻略の計画を放棄して、小笠原諸島を攻略後に沖縄に侵攻することが決定された[11]。作戦名は「デタッチメント作戦(分断作戦)」と名付けられたが、のちに「海兵隊史上最も野蛮で高価な戦い」と呼ばれることにもなった[12]。
作戦は、ダグラス・マッカーサーによるレイテ島の戦いやルソン島の戦いが計画より遅延したことで2回の延期を経て[13]、1945年2月19日にアメリカ海兵隊の硫黄島強襲が艦載機と艦艇の砲撃支援を受けて開始された。上陸から約1か月後の3月17日、栗林忠道陸軍中将(戦死認定後陸軍大将)を最高指揮官とする日本軍硫黄島守備隊(小笠原兵団)の激しい抵抗を受けながらも、アメリカ軍は同島をほぼ制圧。3月21日、日本の大本営は17日に硫黄島守備隊が玉砕したと発表する。しかしながらその後も残存日本兵からの散発的な遊撃戦は続き、3月26日、栗林大将以下300名余りが最後の総攻撃を敢行し壊滅、これにより日米の組織的戦闘は終結した。アメリカ軍の当初の計画では硫黄島を5日で攻略する予定であったが、最終的に1ヶ月以上を要することとなり、アメリカ軍の作戦計画を大きく狂わせることとなっ
自決前、大田中将が海軍次官にあてた電文(全文)
知る戦争
2021年8月11日 12時00分
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
list
noteで書く
はてなブックマークでシェアする
メールでシェアする
印刷する
写真・図版
沖縄の海軍司令官だった大田実氏(中央)一家の家族写真=板垣愛子さん提供
[PR]
76年前の1945年6月、沖縄の地下に掘られた洞穴で、一人の軍人が自ら命を絶ちました。海軍司令官の大田実海軍中将。自決直前に海軍次官にあてた電文では、沖縄戦の惨状と沖縄県民の献身をつづり、「後世特別の配慮を」と訴えました。
大田司令官の自死「貧困のどん底」 海を渡った娘の願い
大田実司令官が出した電文
(旧海軍司令部壕ホームページより)
《原文》
062016番電
発 沖縄根拠地隊司令官
宛 海軍次官
左ノ電■■次官ニ御通報方取計(とりはからい)ヲ得度(えたし)
沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルベキモ 県ニハ既ニ通信力ナク 三二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メラルルニ付 本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非(あら)ザレドモ 現状ヲ看過スルニ忍ビズ 之(これ)ニ代ツテ緊急御通知申上グ
沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来 陸海軍方面 防衛戦闘ニ専念シ 県民ニ関シテハ 殆(ほとん)ド 顧(かえり)ミルニ 暇(いとま)ナカリキ
然(しか)レドモ本職ノ知レル範囲ニ於(おい)テハ 県民ハ青壮年ノ全部ヲ防衛召集ニ捧ゲ 残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家屋ト家財ノ全部ヲ焼却セラレ 僅(わずか)ニ身ヲ以テ軍ノ作戦ニ差支(さしつかえ)ナキ場所ノ小防空壕ニ避難 尚砲爆撃下■■■風雨ニ曝(さら)サレツツ 乏シキ生活ニ甘ンジアリタリ
而(しか)モ若キ婦人ハ率先軍ニ身ヲ捧ゲ 看護婦烹炊(ほうすい)婦ハモトヨリ 砲弾運ビ 挺身(ていしん)斬込隊スラ申出ルモノアリ
所詮(しょせん) 敵来リナバ老人子供ハ殺サレルベク 婦女子ハ後方ニ運ビ去ラレテ毒牙ニ供セラルベシトテ 親子生別レ 娘ヲ軍衛門ニ捨ツル親アリ
看護婦ニ至リテハ軍移動ニ際シ 衛生兵既ニ出発シ身寄リ無キ重傷者ヲ助ケテ■■ 真面目ニテ一時ノ感情ニ駆ラレタルモノトハ思ハレズ
更ニ軍ニ於テ作戦ノ大転換アルヤ 自給自足 夜ノ中ニ遥ニ遠隔地方ノ住居地区ヲ指定セラレ輸送力皆無ノ者 黙々トシテ雨中ヲ移動スルアリ 之ヲ要スルニ陸海軍沖縄ニ進駐以来 終止一貫
勤労奉仕 物資節約ヲ強要セラレツツ(一部ハ■■ノ悪評ナキニシモアラザルモ)只管(ひたすら)日本人トシテノ御奉公ノ護ヲ胸ニ抱キツツ 遂ニ■■■■与ヘ■コトナクシテ 本戦闘ノ末期ト沖縄島ハ実情形■■■■■■
一木一草焦土ト化セン 糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂(い)フ 沖縄県民斯(か)ク戦ヘリ
県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ 賜ランコトヲ
(■は判読できず)
《現代語訳》
昭和20年6月6日 20時16分
次の電文を海軍次官にお知らせ下さるよう取り計らって下さい。
沖縄県民の実情に関しては、県知事より報告されるべきですが、県にはすでに通信する力はなく、32軍(沖縄守備軍)司令部もまた通信する力がないと認められますので、私は、県知事に頼まれた訳ではありませんが、現状をそのまま見過ごすことができないので、代わって緊急にお知らせいたします。
沖縄に敵の攻撃が始って以来、陸海軍とも防衛のための戦闘に専念し、県民に関しては、ほとんどかえりみる余裕もありませんでした。しかし、私の知っている範囲では、県民は青年も壮年も全部を防衛のためかりだされ、残った老人、子供、女性のみが、相次ぐ砲爆撃で家や財産を焼かれ、わずかに体一つで、軍の作戦の支障にならない場所で小さな防空壕に避難したり、砲爆撃の下でさまよい、雨風にさらされる貧しい生活に甘んじてきました。
しかも、若い女性は進んで軍に身をささげ、看護婦、炊飯婦はもとより、防弾運びや切り込み隊への参加を申し出る者さえもいます。敵がやってくれば、老人や子供は殺され、女性は後方に運び去られて暴行されてしまうからと、親子が行き別れになるのを覚悟で、娘を軍に預ける親もいます。
看護婦にいたっては、軍の移動に際し、衛生兵がすでに出発してしまい、身寄りのない重傷者を助けて共にさまよい歩いています。このような行動は一時の感情にかられてのこととは思えません。さらに、軍において作戦の大きな変更があって、遠く離れた住民地区を指定された時、輸送力のない者は、夜中に自給自足で雨の中を黙々と移動しています。
これをまとめると、陸海軍が沖縄にやってきて以来、県民は最初から最後まで勤労奉仕や物資の節約をしいられ、ご奉公をするのだという一念を胸に抱きながら、ついに(不明)報われることもなく、この戦闘の最期を迎えてしまいました。
沖縄の実績は言葉では形容のしようもありません。一本の木、一本の草さえすべてが焼けてしまい、食べ物も6月一杯を支えるだけということです。
沖縄県民はこのように戦いました。県民に対して後世特別のご配慮をして下さいますように。
大田司令官の自死「貧困のどん底」 海を渡った娘の願い
◇
おおた・みのる 1891年、千葉県生まれ。海軍の中でも
1945年、占守島…日本を分断から救った男たち
#樋口季一郎
https://shuchi.php.co.jp/rekishikaido/detail/2637
Twitter
シェア
LINEで送る
linkedin
2015年11月25日 公開
2022年08月25日 更新
早坂隆(ノンフィクション作家)
占守島
終戦後の「忘れられた戦い」
日本は昭和20年(1945)の何月何日に戦争を終えたのか――。この問いに「8月15日」と答えない日本人はまずいないと思います。一方、大東亜戦争(太平洋戦争)における「地上戦が行なわれた日本の領土」といえば、多くの方が「沖縄」を連想することでしょう。
しかし、「終戦の日」の2日後、昭和20年8月17日の深夜、紛れもない日本の領土で始まった戦いが存在したことについては、知る人が少ないように思えます。日本領千島列島の北東端・占守島(しゅむしゅとう)に不法侵攻してきたソ連軍に対し、日本軍が祖国を守るべく戦った「占守島の戦い」です。現在の北方領土問題へとつながる出来事でもありました。
かく言う私も、占守島の戦いについてある程度の知識はあったものの、「どのような戦いだったか」「どんな意義があったのか」を詳しく知ったのはここ数年のことです。関心を抱いたきっかけは、樋口季一郎中将でした。
樋口は昭和13年(1938)、杉原千畝よりも前にナチスからユダヤ人を救った人物で、占守島の戦いでは北方を守る第五方面軍の司令官としてソ連軍への反撃を命じました。そんな樋口の手記を入口に、私は占守島の戦いについて調べ始めたのです。
運命の、昭和20年8月17日深夜
最も印象的なのが、樋口の孫・隆一さんから伺った逸話です。隆一さんは、季一郎から次のような話を聞かされたと教えてくれました。
「日本の歴史家は、あの戦争の負け戦ばかりを伝えている。しかし、中には占守島の戦いのような勝ち戦もあったし、だからこそ今の日本の秩序や形が守られている。
負け戦を語ることも大事だが、その一方で、重要な勝ち戦があったことについても、しっかりと語り継いでほしい……」
自らの功を、公に喋るような人物では断じてない。取材を通じて樋口に抱いた印象です。そんな樋口が、占守島の戦いを「語り継いでほしい」と漏らしたのは、なぜなのか。樋口の胸の裡は、あの戦いの「意義」を知ればおのずと見えてきます。
占守島は今もなお、ロシアに実効支配されており、その存在すら学校の授業でも教えられることはありません。
占守島は千島列島の北東端に位置し、戦争当時は日本の領土でした。なお、国際法上、占守島だけでなく全千島列島と、南樺太も日本領として認められていました。
昭和20年当時、日本の北東の国境の最前線にあたる占守島には、約8,000の日本陸海軍将兵がいたとされます。ソ連と国境を接していますが、「日ソ中立条約」を結んでいたため、あくまでもアメリカ軍への備えです。
しかし――8月17日深夜、占守島に攻め込んできたのは、相互不可侵を約していたはずのソ連軍でした。ソ連は中立条約を一方的に破棄するという明らかな国際法違反を犯し、日本を「騙し討ち」したのです。
ソ連軍は8月9日にすでに満洲に侵攻していましたが、そこで行なわれたのは戦闘行為ですらありません。殺人、略奪、家屋侵入、そして強姦……。彼らは同じような手法で、千島列島の他、南樺太までも攻略しようと企みました。
北海道までを狙うソ連の野望
発端は、同年2月のヤルタ密約にまで遡ります。アメリカのルーズベルト、イギリスのチャーチル、ソ連のスターリンが会談を行ない、ソ連が対日参戦を条件に千島列島や南樺太を獲得することを秘密協定で認めたのです。
しかし、スターリンはやがて、北海道の北半分の領有までも主張し始めました。対するアメリカはこれを拒否。後の冷戦構造の萌芽ですが、遺憾にも真っ先に巻き込まれたのが日本でした。
ソ連は終戦近しと見るや、千島列島や南樺太への侵攻を開始。どさくさに紛れて日本領を少しでも掠め取ろうとしたのです。あのスターリンならば、千島列島、北海道を獲った後、勢いに乗じて本州の東北地方の占領までをも窺ったであろうことは想像に難くありません。
結果、日本は戦後のドイツや朝鮮半島と同じような分断国家になっていたかもしれないのです。なお、日本側は当初、そんなソ連に和平の仲介役を期待していました。そんな史実も、あの戦争の一側面として知っておくべきでしょう。
陸軍きってのロシア通だった樋口は、「ソ連軍、来襲」の報に接した瞬間、ソ連の野望と日本が直面した未曾有の危機を鋭敏に察しました。戦後、樋口が「占守島の戦いが今の日本の秩序や形を守った」と指摘したのはそのためです。
樋口は誰よりも占守島の戦いの意義を知るからこそ、占守島で敢然と起ち上がり、肉弾と散った部下たちの姿を後世の日本人にも知って欲しいという「本音」を孫の隆一さんに語ったのでしょう。
次のページ
故郷に帰る夢を脇に置いて >
←
1
2
3
→
妻を後部座席に乗せソ連軍へ特攻~書評『妻と飛んだ特攻兵』に涙
2022/08/18
https://bushoojapan.com/historybook/2022/08/18/3604
日本初の歴史戦国ポータルサイト
BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)
8月15日は終戦記念日。
その終戦から4日後の8月19日、戦闘機でソ連軍に特攻した夫婦がいました。
戦闘機に、ワンピースの黒髪の女性が乗っているという「絵」はジブリ映画にでもありそうですが、これが本当に起きた史実だったのです。
ノンフィクション作家の豊田正義氏が刊行した『妻と飛んだ特攻兵(→amazon)』で初めて明らかにされました。
後にドラマ放送もされ、成宮寛貴さんと堀北真希さんが演じられておりましたが、一体どんな史実だったのか。
書評を兼ねて確認してみたいと思います。
※ドラマはAmazonプライム・ビデオで視聴できます(→amazon)
お好きな項目に飛べる目次 [とじる]
1ページ目
艶やかな光を湛えて風になびく黒髪が
元会津藩士の子孫と北海道出身の少尉
2ページ目
ソ連の虐殺に耐えかね特攻を決意する
艶やかな光を湛えて風になびく黒髪が
ときは昭和20年8月19日――。
満州の飛行場を11機の九七式戦闘機(を改造した訓練機)が飛ぼうとしていました。
この時点日本はすでに降伏しています。
ソ連に対して飛行機を受け渡すためのフライトでした。
11人の操縦士を見守る多くの日本人。
操縦士の近くには、その家族でしょうか。
白いワンピースに日傘を差した2人の女性がいました。
誰もが見送りと思ったその女性たちは、自分の夫の飛行機の後部座席に乗り込むのです(一人は愛人でした)。
11人は、命令に反し、満州で日本人の虐殺を続けるソ連軍に一矢報いるため、特攻を密かに計画していたのです。
夫の覚悟についていこうと決めた2人の若い女性。
女性を乗せた2機が滑走路を走り出したとき、群衆たちはようやく異変に気付きました。
「艶やかな光を湛えて風になびく黒髪が目撃されたのだ」(306頁)
元会津藩士の子孫と北海道出身の少尉
「神州不滅特攻隊」を名乗った11人(+2人)は、
「戦い得ずして戦わざる空の勇士十一名 生きて捕虜の汚辱を受けるを忍び難し」
との遺書を残していました。
九七式戦闘機/wikipediaより引用
10機(1機は離陸直後にエンジン不調で墜落)の行方は分かりません。
特攻が成功したのか否か。
それは歴史の闇に消えました。
戦後、関係者の間で、「女性を特攻機に乗せた」ことが軍規違反とされ、彼らが「英霊」から外されたり、その後、仲間たちが名誉回復をしたりと、元軍関係者の間では密かに知られておりましたが、世間に出されるのは本書が初めてとのことです。
ひと組は夫婦で、青森出身の谷藤徹夫・朝子夫妻。
谷藤家は、元会津藩士の子孫(戊辰戦争後に下北半島に移住した末裔)だそうです。
斗南藩
斗南藩の生き地獄~元会津藩士が追いやられた御家復興という名の流刑
続きを見る
もうひと組は、北海道出身の少尉と現地で恋愛関係にあった宿の女中さんでした。
惜しいのは、取材に応じたのが11人のうち「谷藤家」関係者だけだったことです。
※続きは【次のページへ】をclick!
大東亜戦争は日本が勝った -英国人ジャーナリスト ヘンリー・ストークスが語る「世界史の中の日本」 単行本 - 2017/4/17
ヘンリー・S・ストークス (著), 藤田 裕行 (翻訳)
5つ星のうち4.5 128個の評価
単行本
¥1,760
獲得ポイント: 80pt
¥250 より 38 中古品¥1,760 より 29 新品¥3,520 より 1 コレクター商品
普及版 大東亜戦争は日本が勝った
¥1,320
(128)
残り12点(入荷予定あり)
________________________________________
「太平洋戦争」はアメリカの洗脳だった
この書は日本のプロパガンダではない。史実である。
日本よ 呪縛から解放されよ!
ヘンリー・S・ストークス 来日50年の総集編
世界史を俯瞰して明らかになった
大東亜戦争の真実
共産党などの左翼は、大東亜戦争は「侵略戦争」であったと言う。
そうであろうか? 史実を検証すると、そこには明らかに「アジア解放戦争」の側面が見て取れる。
アメリカの侵略戦争や、大英帝国の植民地支配での戦争とは、明らかに違った姿を現じている。
私は、大東亜戦争を日本がなぜ戦ったのか、その結果、何が世界に起こったのかは、
世界文明史的な俯瞰をもってしてはじめて、明らかになるものだと、そう思い始めた。
世界文明史の中で、大東亜戦争を位置づけようというような野心的な試みは、一冊の本で果たせるものでもないが、
その第一歩を英国人ジャーナリストの私が切り開くことで、世界中に多くの賛同者が出てくると、
そう確信している。(本文より)
1章 日本が戦ったのは「太平洋戦争」ではない!
2章 「太平洋戦争」史観で洗脳される日本
3章 日本は「和」の国である
4章 世界に冠たる日本の歴史
5章 オリエントにあった世界の文明と帝国
6章 侵略され侵略するイギリスの歴史
7章 アメリカの「マニフェスト・デスティニー」
8章 白人キリスト教徒による太平洋侵略
9章 マッカーサー親子によるフィリピン侵略
10章 大日本帝国と西欧列強の帝国主義の違い
11章 大日本帝国は「植民地支配」などしていない!
12章 日本は中国を侵略していない
13章 アメリカによる先制攻撃の「共同謀議」
14章 大統領がアメリカ国民を欺いた日
15章 大英帝国を滅ぼしたのは日本だった!
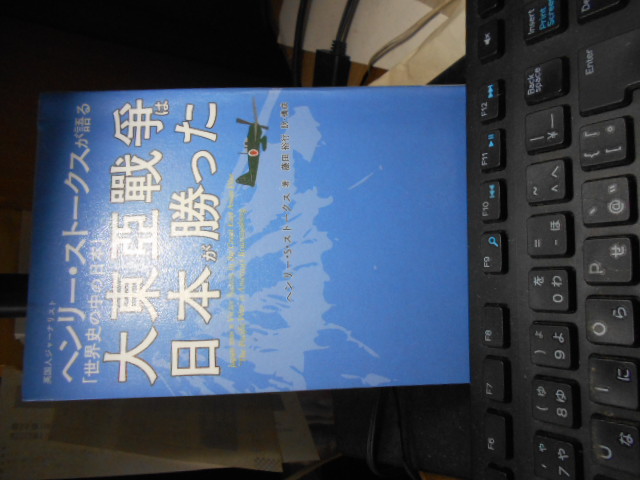
「世界から恐れられた7人の日本人」上巻
世界世界
せ
※下巻は、上巻購入後、次のページでご案内しております
1人目:日本軍 20 万に匹敵する男 -明石元二郎陸軍大佐
○帝政ロシアを揺るがし、 日露戦争を勝利へ導く
○明石を支援した日本陸軍のスパイマスターたち
○ジェームス・ボンドも明石の味方に! ?
2人目:米国務長官が欲しがった男 ―岩畔豪雄陸軍少将
○「世界基準の戦い方」をプランニングし、遂行する
○アメリカとの戦争回避に奔走
○インドの独立運動にも大きく貢献
3人目:日本のスパイマスタ― ―秋草俊陸軍少将
○インテリジェンス教育の総本山「中野学校」を創設
○猛者ぞろいの中野学校出身者
○謀略から特攻まで、 ただ目標完遂のために
4人目:インドを独立に導いた謀略の素人 ―藤原岩市陸軍少佐
○5万ものインド人捕虜の心を一瞬にしてつかむ
○曲解され悪魔化される日本のナショナリストたち
5人目:日本版アラビアのロレンス ― 鈴木敬司陸軍大佐
○親日ミャンマーの原点は鈴木大佐にあり
○「アジアはアジア人の手に」を願い共に戦った野田毅陸軍大尉
○日本が掲げた理想、そして誠の心がアジア諸国を動かした
6人目:アメリカ軍の動きを的確に予測した情報のプロ ―堀栄三陸軍少佐
○株価の動きでアメリカ軍の動きを予測
○その情報は、 陸軍大本営の参謀によって握りつぶされた
○米軍戦法の研究書を執筆し、日本軍の戦いに貢献
○アメリカ軍を壊滅状態に追い込んだ堀の教え
7人目:MI5が徹底監視した唯一の日本人 ―小野寺信陸軍少将
○各国のスパイマスターたちに引けを取らない諜報力
○握りつぶされた「ヤルタ会談の密約」情報
世界を変えてきた比類なき日本のインテリジェンス
あとがき:ウィズコロナ時代だからこそ、先人のインテリジェンスに学べ
著者プロフィール
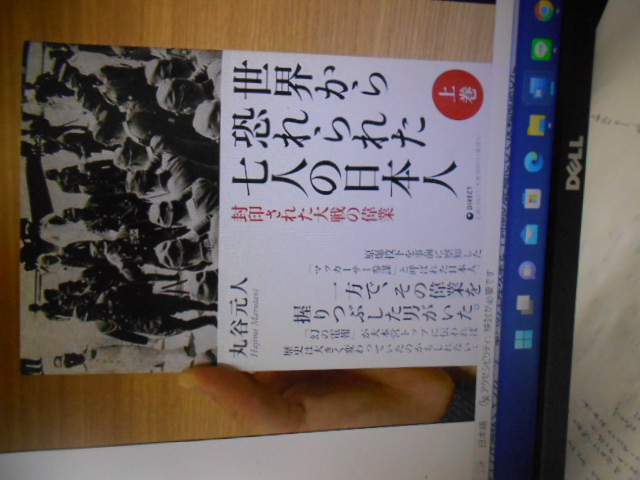
大東亜共同宣言(だいとうあきょうどうせんげん、大東亞共同宣言)
大東亜共同宣言(だいとうあきょうどうせんげん、大東亞共同宣言)は、1943年(昭和18年)11月6日に大東亜会議にて採択された共同宣言。大東亜宣言とも。
概要
東京・帝国議事堂で同年11月に開催されたアジア地域の首脳会議の2日目に満場一致で採択された。採択後にビルマ国代表のバー・モウ内閣総理大臣が「自由インドなければ自由アジアなし」とインド独立を支持する意見を述べ、陪席者(オブザーバー)として出席した自由インド仮政府のチャンドラ・ボース首班が自由インドの確立を表明した[1]。次いで日本の東條英機内閣総理大臣が自由インドへの強い支援を会議で表明、大東亜会議は閉会した。
参加国
日本 : 東條英機内閣総理大臣、外務省・大東亜省などの各大臣、総裁、書記官など
中国 : 汪兆銘国民政府行政院長、行政院副院長、外交部部長など
タイ : ワンワイタヤーコーン親王(首相代理)、外務省など
満洲 : 張景恵国務総理大臣、外交部大臣、特命全権大使など。
フィリピン : ホセ・ラウレル大統領、外務大臣、大統領秘書など
ビルマ : バー・モウ内閣総理大臣、特命全権大使、外務次官など
インド:チャンドラ・ボース(首班)、最高司令部参謀長など
宣言全文
原文
大東亞共同宣言
抑?世界各國ガ各其ノ所??ヲ得相倚リ相扶ケテ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ世界平??和確立ノ根本要義ナリ
然ルニ米英ハ自國ノ繁榮ノ爲ニハ他國家他民族ヲ抑壓シ特ニ大東亞ニ對シテハ飽??クナキ侵略搾取ヲ行ヒ大東亞隷屬化ノ野望??ヲ逞ウシ遂??ニハ大東亞ノ安定ヲ根柢ヨリ覆サントセリ大東亞戰爭ノ原因茲ニ存ス
大東亞各國ハ相提携シテ大東亞戰爭ヲ完遂??シ大東亞ヲ米英ノ桎梏ヨリ解放シテ其ノ自存自衞ヲ全ウシ左ノ綱領ニ基キ大東亞ヲ建設シ以テ世界平??和ノ確立ニ寄與センコトヲ期ス
一、大東亞各國ハ協同シテ大東亞ノ安定ヲ確保シ道??義ニ基ク共存共榮ノ秩序ヲ建設ス
一、大東亞各國ハ相互ニ自主獨立ヲ尊??重シ互助敦睦ノ實ヲ擧ゲ大東亞ノ親和ヲ確立ス
一、大東亞各國ハ相互ニ其ノ傳統ヲ尊??重シ各民族ノ創造??性ヲ伸暢シ大東亞ノ文化ヲ昂揚ス
一、大東亞各國ハ互惠ノ下緊密ニ提携シ其ノ經濟發展ヲ圖リ大東亞ノ繁榮ヲ增進??ス
一、大東亞各國ハ萬邦トノ交誼ヲ篤ウシ人種的差別ヲ撤廢シ普ク文化ヲ交流シ進??ンデ資源ヲ開放シ以テ世界ノ進??運??ニ貢獻ス
口語訳
そもそも世界各国がそれぞれその所を得、互いに頼り合い助け合ってすべての国家がともに栄える喜びをともにすることは、世界平和確立の根本です。
しかし米英は、自国の繁栄のためには、他の国や民族を抑圧し、特に大東亜(東アジア全般)に対しては飽くなき侵略と搾取を行い、大東亜を隷属化する野望をむきだしにし、ついには大東亜の安定を根底から覆(くつがえ)そうとしました。大東亜戦争の原因はここにあります。
大東亜の各国は、互いに提携して大東亜戦争を戦い抜き、大東亜諸国を米英の手かせ足かせから解放し、その自存自衞を確保し、次の綱領にもとづいて大東亜を建設し、これによって世界の平和の確立に寄与することを期待しています。
大東亜各国は、協同して大東亜の安定を確保し、道義に基づく共存共栄の秩序を建設します。
大東亜各国は、相互に自主独立を尊重し、互いに仲よく助け合って、大東亜の親睦を確立します。
大東亜各国は、相互にその伝統を尊重し、各民族の創造性を伸ばし、大東亜の文化を高めます。
大東亜各国は、互恵のもとに緊密に提携し、その経済発展を図り、大東亜の繁栄を増進します。
大東亜各国は、すべての国との交流を深め、人種差別を撤廃し、広く文化を交流し、すすんで資源を開放し、これによって世界の発展に貢献します。
作成の経緯
本文の5項目に関しては、1943年(昭和18年)8月初旬には外務省内「戦争目的研究会」で大西洋憲章(1941年)なども大いに参考にするかたちで文案作成がはじまり、同10月には完成したものとみられる[2]。これと別途並行して大東亜省は大川周明[3][4]や矢部貞治に宣言案を作成させており、それは前文として追加されることになった。大西洋憲章を参考にした本文が普遍的な真理を提唱するのに対し、大東亜省の前文は「米英支配の打破」という時事的な記述に偏っており、論理の接続が悪い所以とされる。
日本を除く大東亜会議参加国は、会議2週間前になりようやく意見聴取の場を得たが、修正意見は日本側にことごとく拒絶され、結局一字一句の変更もなされずこの文面のまま全会一致で採択された。